広島市 舟入橋塗替 循環式ブラストを用いて塗膜除去
広島市は中区の舟入川口町と吉島町をつなぐ広島市道吉島観音線の(旧太田川)本川を渡河する箇所にある舟入橋の塗り替えを進めている。直下は宮島と平和記念公園を行き来する観光船が通る航路が設定されている。そのため航路上にある支間(P2~P3)の桁はあえて箱桁とし、桁高を(他の径間の鈑桁に比べ)低くして、観光船とのクリアランスを確保していることが特徴である。1969年6月に桁は製作され、橋の供用そのものは1970年3月である。塗替え履歴は1度あり、その際はRC-Ⅲで塗り重ねが行われた。既設塗膜厚は350~400μm程度だが、PCBや鉛が検出されているため、安全かつ廃棄物を減らす形で撤去するべく循環式ブラストを用いて既設塗膜を除去する手法を採用している。その現場を取材した。(井手迫瑞樹)
1次ブラスト(塗膜除去ブラスト)1日当たりの施工面積は270㎡
塗替え部位、面積はA1~P3間の3,180㎡
2基4ノズル体制で施工
同橋は橋長164m、最大支間長24.2m、最大幅員18.7mの単純鋼I桁2連+単純鋼箱桁+単純鋼I桁4連の橋梁である。支間長は両端部が19.36m、そのほかは24.2mとなっている。24時間交通量は 12496台、大型車混入率は6.6%(830台)(いずれも交通量及び大型車混入率は令和3年度全国道路・街路交通情勢調査より)である。今回施工したのは左岸側のA1~P3で箱桁部が含まれており、今次3径間の塗替え面積は3,180㎡に達している。

左岸側のA1~P3 約3,180㎡を塗り替える(井手迫瑞樹撮影)
主桁や横桁等の上部工鋼部材については、PCBの含有が認められたことや経年劣化による腐食、防食機能の劣化が全体的に見られたため、機能回復及び劣化因子遮断を目的として塗替え塗装による補修を行うこととした。
さらに、剥離剤を用いた剥離工法と従来のブラスト工法及び循環式ブラスト工法において、塗装の剥ぎ取りや塗替えに係る費用、ケレンかす等の発生量、品質について比較検討を行った結果、循環式ブラストが最も優れていたため採用した。本橋では、非出水期内の短期間で施工する必要があることからも効率的な塗替えが行える循環式ブラスト工法が優位に立った。


循環式ブラストの設備(井手迫瑞樹撮影)
循環式ブラストは1基4ノズル体制で施工している。1次ブラスト(塗膜除去ブラスト)1日当たりの施工面積は270㎡に達する、一次ブラストを1径間完了後、2次ブラスト(ジンク施工が4h以内にできる範囲1回あたり600~700㎡)を施工し、ジンク以降の塗替え塗装を施す、ということを繰り返していく。


ブラスト施工状況(大政建設工業提供)




ブラスト施工前と施工後の状況(左2枚は鋼床版裏面、右2枚は鈑桁部)(大政建設工業提供)


研削材の回収状況
コンクリート補修工も同時施工、間仕切りを設置して塗替えを進める
必ず送気マスク型のエコクリーンスーツを着用したうえで施工
同橋を施工するに当たって、課題となるのがコンクリート補修工との施工上の取り合いである。本現場では、工期の関係上、床版などコンクリート部材の断面修復、ひび割れ注入・同充填工、表面含浸工(MCI-2018)、沓座モルタルの補修工、鋼製フィンガージョイントの止水工などを並行して行う必要がある。そのため、お互いの品質に影響しないように補修工と塗替え工の間で間仕切りを設置しつつ施工していた(1径間・2径間・3径間ごとに間仕切りを行い、狭い個所を負圧空間にした。)。

間仕切りを設置して施工した
安全面においては、高欄を利用して足場を吊り支持しているが、外側の路面高や地覆天端位置に配慮する形で、高欄内側まで板張りにて全面囲いを設置し、さらに板張り内側をエコクリ-ンシートにて目張り養生を設置して負床集塵機にて負圧空間になるようにし、外部に粉塵が出ないようにしている。
さらに場内で作業する労働者は、必ず送気マスク型のエコクリーンスーツを着用したうえで施工し、ブラストにより発生する粉塵から守る形で施工を行っている。また、集塵装置を設置し、場内全体を15分に1回完全換気し、安全性と施工性の向上に努めている。
現在はブラストがほぼ完了し、塗装もほぼ完了している。
設計は荒谷建設コンサルタント。元請は大政建設工業。 一次下請は宮本塗装工業、ファーストテクノ(橋梁塗装工)、哲組(仮設工)、YISグループ(交通誘導)。主要二次下請は真和塗装工業。






-のコピー.jpg)


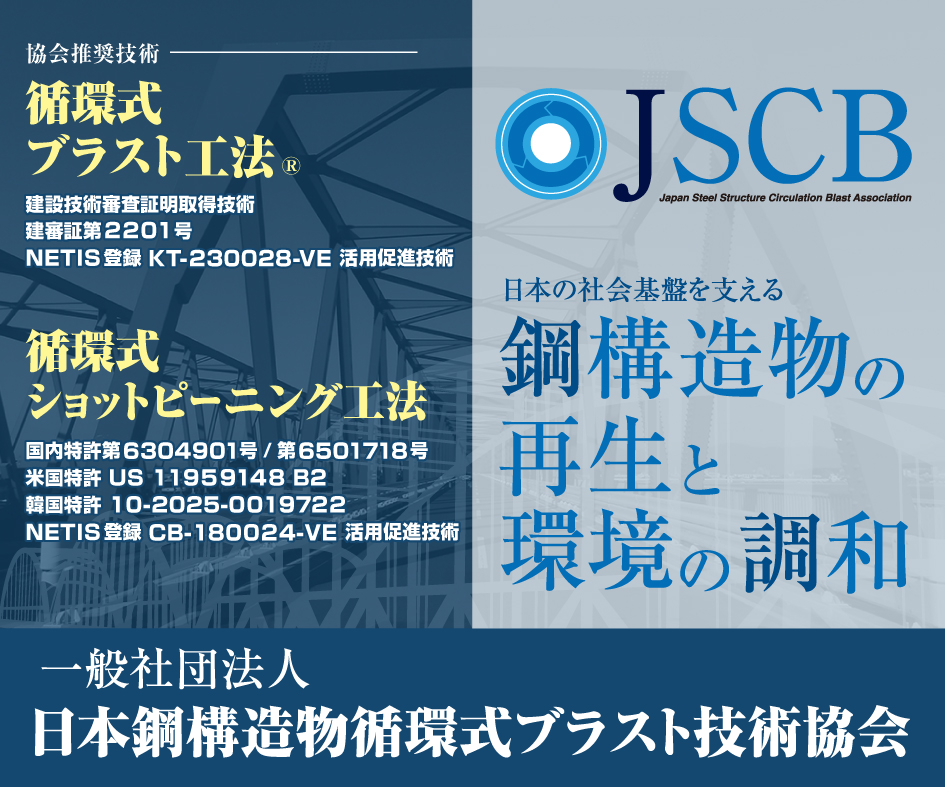


 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら