新しい時代のインフラ・マネジメント考
4.思い込みは危険
思い込みは危険である。わかったつもり。わかっているつもり。では物事は達成できない。また、先にも書いたが批判は多いがその解決策は示せない人たち。もっともわたしは、戦略的に、わざと批判している。批判して、相手がどう出てくるか探っている。答えは一つではないので、どう取り組むかの方が重要である。しかし、自分たちの開発したものやっていることに対して、自信があるのは良いのだが思い込みの激しい人たちが多い。
世の中は複雑であるので、あそこでうまくいったからと言って、ここでうまくはいかない場合もある。私が経験したのは、「橋のお掃除」である。これは、1手法として橋の延命化につながると思い10年前に、導入を試みた。ある橋が錆びていて、みっともないと言うので、安全な場所だけでも子供や住民の方でペンキを塗ってもらおうかということを提案したところ、議員さんが地元をまとめると言うので、内容を説明するための説明会を行った。
危険な場所は専門業者にも入ってもらう。材料(ペンキ)は、市で購入し、塗装業協会への協力を依頼した。現場での安全管理は重要なので、市の職員と塗装業協会の有志に同席してもらうということで話した。地元の要望を聞き、多くの方々が参加できる平日の夜19時から2度にわたり実施した。すると、最初はやりたいと言っていたはずの住民の中から、「日当は出るのか?刷毛は? 軍手は? 支給されるのか?」という意見が出てきた。「道具は要望があれば支給しますが、日当は無理」というと、紛糾し話がまとまらない。
「なんで市の物を俺たちがやらなければ、ならないのか?」という意見が強まり、議員さんと話て、「これでは無理ですね。こちらも無理してやっていただかなくても。」という話になり、取りやめた。それを市長に話すと「富山では無理だと思うよ。そういう無駄なことに時間を使うな。」と言われ、その後はボランティア的発想は、辞めることにした。
しかし、世の中の風潮は、住民参加が評価されている。職員の中からも、住民参加事業をやりたいと言う声はある。しかしうまくいかないのが現実である。ボランティアの代表を自主的にやられている代表の方とも話したが、「ここでは無理ですね。私たちも苦労している。」「ボランティア活動をしていると、通行人に「おばちゃん、この仕事日当はいくらだ?」と聞かれる。」という話。住民参加型の難しさを感じた。
5.まとめ
最近特に感じるのが、今回も書いた、①勝手な解釈、②わかったふり、③反論好き。である。まあ、皆さんいろいろ考えているということであろうが、これって危ういです。物事を停滞させるきっかけになりますし、反対派に付け込まれる。
少なくとも我々は課題を解決していかねばならない。課題解決には、様々な手法の試行や、外力に対し抵抗する労力、耐力がいる。何でも反対する人たちの多くは素人であることが多いが、一応専門家やプロの方もいる。しかし、反対する前に、反対するくらいならば自分でやればよい。これは机上論しか考えない人たちにも多い。やってみて、どうなるかやってみればよいだけである。わざわざ、「あれはおかしい」とか「あれはだめだ」という方々が実に多いが、ならば自分たちでよいと思うことをやればよいだけなのである。世の中でやれらている手法も自分たちの手法も、それぞれがうまくいけばこれは、世の中のためなのである。認められるには労力と時間がかかる。



やっと、補修オリンピックの価値が認められだした。富山市管理のフィールドを提供し実証実験
最近、八潮の事故などでも、議論が活発になっているが、今後の在り方において「新技術の導入と、マネジメント」と言われている。地上から地下空間を見る技術に電磁波レーダーがあるが、これも勝手な話が先行している。私の経験からでは、地上から2m程度までは見える可能性があるがそれ以上は能力的に無理がある。以前から「3mまで見れます」とか様々な適当なことを言う業者がいる。しかし、常識的ではない。協議の中でも電磁波の出力を上げれば、というのもあったが現実的ではない。ましてやドローンやAIには限界があるが世の中の風潮はそうではない。ここで、判断を誤れば、無駄なことをする結果にもなりかねないと心配している。まあ、それも管理者の判断である。それぞれ責任感を持つことが重要である。
また、最近特に強く感じるのは、様々なことが言われているが、結局は最初に精度、品質の良いものを造ることである。維持管理には限界があるので、新設時には十分な調査、精度の良い設計、精度の良い施工を実施することである。そしてこれには、「鬼の協議」「鬼の検査官」が必要である。失敗は失敗で報告することも必要であろう。失敗したら、それはリスクとして伝えていかねばならない。まずは、健全なものを今後は作っていくことを明確に言わなければならない。そうでないと、維持管理は進まない。



造った時点での鉄筋不足。結果的に補強策まで必要になる。施工時の問題がリスクとなる見本。
現在は、そのものが健全であったという前提だが決してそうではない。特に管理の甘い自治体に、不健全な構造物が多い。調査も設計も施工も甘いのである。これは様々な理由があったであろう、しかし、負債、リスクである。(次回は9月16日に掲載予定です)


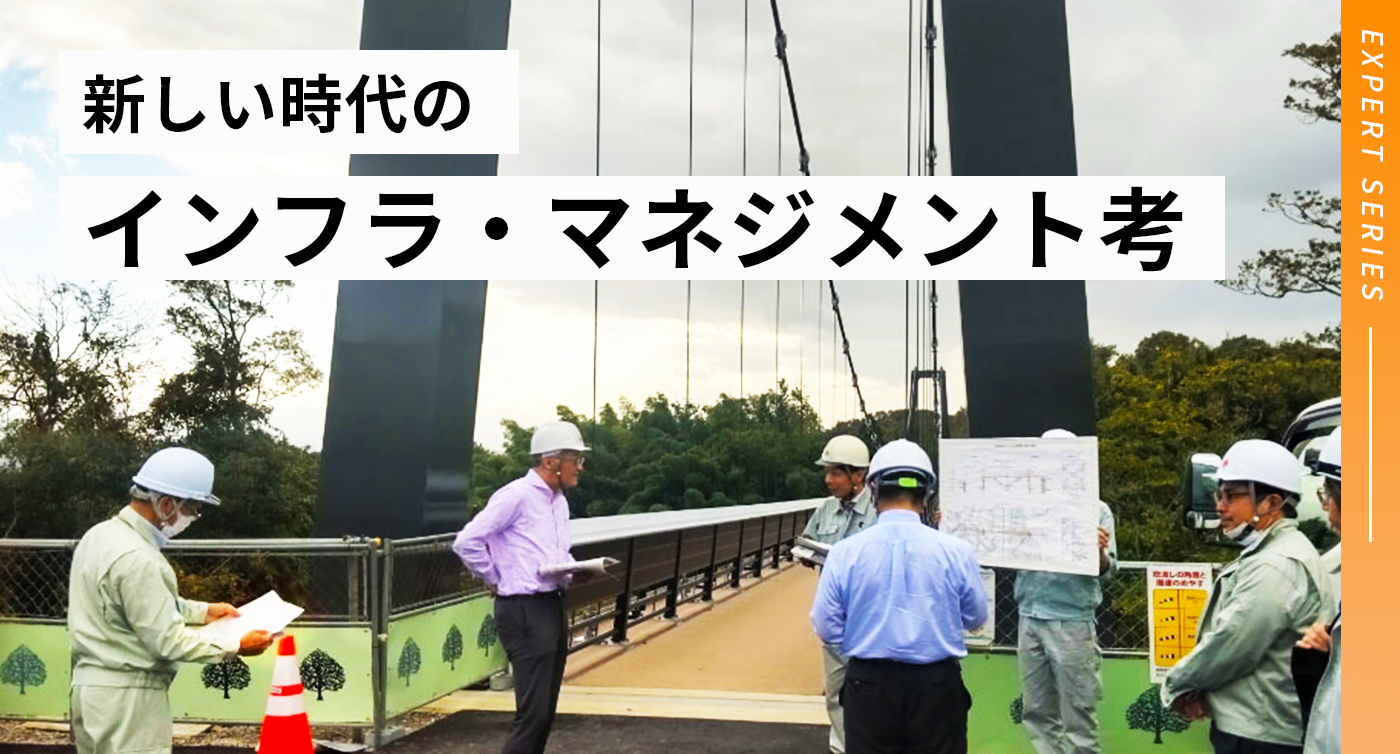





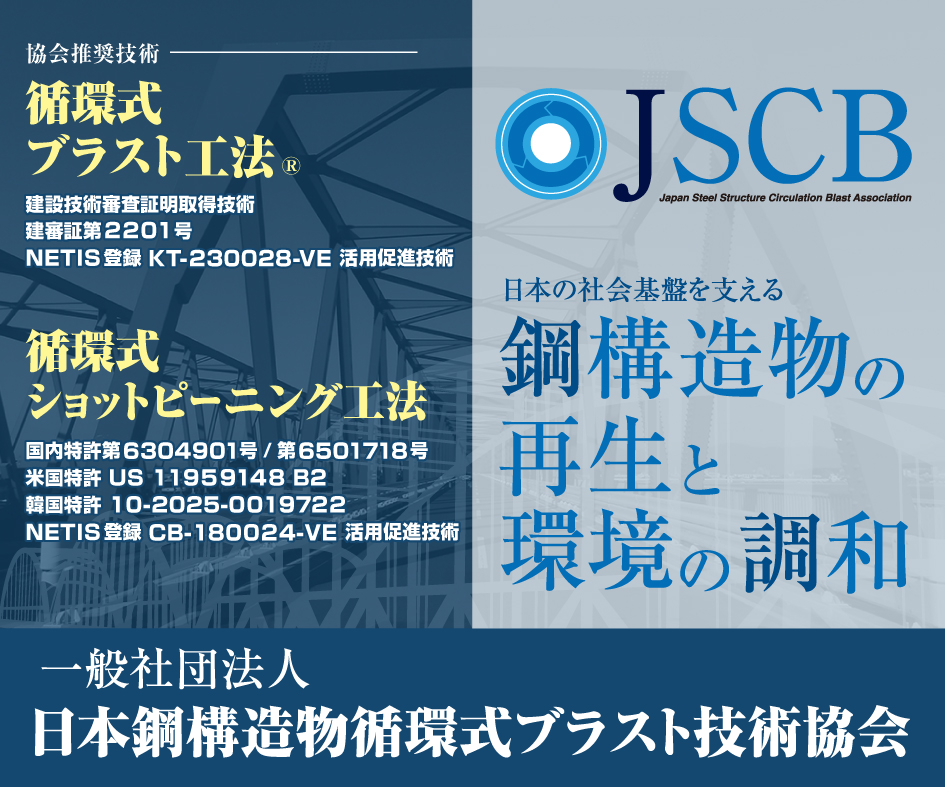





 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら