インフラ未来へのブレイクスルー -目指すは、インフラエンジニアのオンリーワン-
3.我が国の道路橋の設計・施工に関する一考察
多くの社会基盤施設の中で橋は、学ぶ段階で「橋梁工学」等の教科書的な書籍が多くあり、内容は、構造力学・応用力学、材料学、鋼製橋梁・コンクリート製橋梁・プレストレストコンクリート製橋梁の設計・製作・架設、景観など構造的な知識が要求される高度な技術のイメージが強かった。特に、図‐8に示すような研究室におけるモデル橋製作、解析等の実験は、深夜まで行うのが常識でマニアック的な学生が多かったのは事実である。また、道路橋の場合は、「道路橋示方書・同解説」、鉄道橋の場合は、「鉄道構造物等設計標準・同解説」など、読むだけで多くの時間を要する難解書であった。私の専門である道路橋の設計・施工について考えてみる。

図‐8 橋梁研究室での実験風景
3.1 設計基準が早期から体系化・保守的だった
大正関東大震災以降、戦前期から高度経済成長期までに道路橋の設計規定(道路構造令・1919、道路構造に関する細則案・1928、鋼道路橋設計示方書・1939、電弧熔接道路橋設計及び製作示方書案・1940、鋼道路橋設計示方書・1956など)が存在し、1926年の道路構造に関する細則案ではすでに震度法が導入されている。1972年に「道路橋示方書(I共通・II鋼橋)」として統合・制定、1978年にコンクリート編、1980年に下部構造・耐震編が揃い、以降も改訂を継続的に行ってきている。道路橋設計基準の改定作業においては、活荷重(TL20,14‐荷重 → 1993年のA/B活荷重)や細部構造規定が段階的に強化され、結果として“余裕度のある”設計文化が定着したことがあげられる。
3.2 施工・製作時の品質管理が強固
特に我が国の鋼製橋梁は、古くから工場製作・非破壊検査(超音波等)を前提にした工程が標準化されていることが特徴としてあげられる。米国・FHWAの我が国の視察報告(M名誉教授が関与)においても鋼製橋梁製作の品質管理やプレファブの活用(製作工場における自動化)が高く評価されている。米国は、我が国と日米橋梁工学ワークショップ (U.S.–Japan Bridge Engineering Workshop)を1980年代から2010年代まで継続して行っており、2000年前後(平成12~16年頃)の日本側での工場視察・技術交流における公開されている報告が複数ある。中でも2001年に行なわれた Worldwide Steel Bridge Fabrication Scanning Tourにおいては、FHWA と AASHTO が中心となって、日本や欧州の鋼製橋梁製作工場を視察し、鋼製橋梁製作工場での品質管理体制、CAD/CAM の導入状況、仮組立による精度検証、工場自動化技術(溶接ロボット、切断加工機械など)及び発注者検査体制・ファブリケータ認証制度などについて調査している。このWorldwide Steel Bridge Fabrication Scanning Tour報告を読むと、我が国の橋梁製作工場における高精度な鋼桁製作管理、プレファブ活用、工場自動化の進展が、米国チームから特に高く評価されていることが分かる。M名誉教授(日本側代表的研究者)が深く関与した話として「髙木さん、この調査ツアーを行う段階でM社の経営者が自社工場等の優位性を印象付ける視察を画策したこと、それを私の判断で裏工作で退けたことは大きかった。どのようなことがあっても公平・公正だよ、髙木さん分かっているよね」であった。この話を聞いて私は、その時のドロドロした民間会社経営陣の考えとそれを阻止しようとした学の正しい考えを、何とか問題なく纏めようとした主催者側の苦労する姿が脳裏に浮かんだ。
我が国の橋梁製作・架設工事においては、公共機関が発注する工事では共通仕様書・検査規定、レディミクストコンクリートのJISで材料~受入検査まで細密に規定され、現場の品質ばらつきを抑制し今日に至っている。
3.3 過積載・過大車両の“制度的抑制”が古くからあった
橋梁の設計前提を壊す代表的要因の一つは大型車両や過積載車両の過荷重であるが、我が国においては1961年に「車両制限令」(道路法に基づく政令)が制定され、特殊車両通行許可制度を運用開始している。この制度は、私自身も関係者の一員であるが、近年の“簡素化”制度(2022)以前から続く作用荷重を枠内に収める施策である。報告書によると、海外では過荷重・衝突・水理作用(洗掘)が主要な崩壊要因との統計もあり、我が国における先に示す“荷重管理”の徹底によって、崩壊リスクを下げてきた側面が大きいと言える。次に、中小橋梁の標準化設計の話をしよう。
3.4 短~中支間・標準化された形式の多用=設計・施工誤差を低減
わが国の特徴として、山間部が多く平坦の土地が少ない地形や都市部や工場地域の集中等による物流制約から、地方部を中心に短~中支間のRC/PC主桁や合成桁が広く普及している。例えば、PCプレテン桁では輸送制約が支間に上限(概ね~21 m)を与え、地域標準タイプが数多く整備されてきている。我が国が進めてきた道路橋の標準化は設計・施工の再現性を高め、致命的ディテールミスや局部破断からの全体系崩壊の確率を抑制していると思う
3.5 地震国ゆえの“細部”まで行き届いた耐震思想の確立
我が国における耐震は1970年代から体系化し、1995年以降は「落橋梁防止システム(桁かかり長、落橋梁防止装置、変位制限・段差防止)」や支承・取り付け部の設計・検査を大幅に強化して今日に至っている。なかでも、我が国初の落橋防止システムの設置は地震発災時の落橋を狙い撃ちで防ぐ「最後の守り」で、平時の偶発外力(車両衝撃等)に対しても冗長性を提供する仕組みである。諸外国、特に欧米の道路橋と比較して我が国の道路橋は、見るからに構成部材が太く、決してスマートな断面形状とは言えない場合が多々ある。必要最小鉄筋量や被り厚等の規定がプラスに影響していることも事実である。
4.おわりに
本稿では、「なぜ日本の橋は落ちないのか」という問いに対して、設計基準の厳格さ、施工段階の品質管理、維持管理制度の充実、そして安全を最優先する社会的合意の存在といったプラス要因について好意的に整理した。今回の種々の資料を基に行った分析した私の結論として、日本の橋は偶然に落ちないのではなく、長年にわたり多くの技術者によって積み上げられてきた制度と努力の結果として「落ちにくい仕組み」を持っていることが確認できた。しかしながら、「落ちない」という言葉に安住することは極めて危険である。構造物は完成の瞬間から劣化が始まり、気候変動の進行、激甚化する自然災害、さらには高度成長期に大量建設された橋梁群の老朽化といった課題は、我々技術者に不断の警鐘を鳴らしている。安全神話を前提とするのではなく、常に「落ちるかもしれない」という危機感を持ち、最新の知見や技術を活用して継続的な改善を図る姿勢こそが必要である。その理由として、我が国において工事中の仮設・架設段階では倒壊・落橋が多発している(図-9に示す新名神有馬川橋・2016年及び静清バイパス橋桁落下事故架設事故・2023年など)現状があげられる。橋梁架設・建設中の崩落事故発生は、鋼橋、コンクリート橋問わず発生しているが、これら発生の原因は人為的なミスの積み重ねである。一方、幸いなことに供用中橋梁の全体崩落は稀というのが実情である。

図‐9 新名神有馬川橋及び静清バイパス橋桁落下事故
古き昔から現代まで、「災害は忘れたころにやってくる」と良く言われる。だが、我が国における多くの橋は、過去の災害や事故から学び続けることで、世界でも稀な安全性を維持してきた。これからも「災害は忘れたころにやってくる」とならないように、設計・施工・維持管理の各段階で不断の改善を重ね、次の世代へと「落ちない橋」を引き継ぐことが我々の責務である。ここまでが今回の連載の主題、これから後は付け足し、私が執筆した書籍のPRである。
この度、私の経験と知見を最大限生かした「アセットマネジメント・大全 ‐知と技術で築く社会インフラの未来」(図‐10参照)を今月(10月)の初旬に出版し、全国の書店に図-10の書籍に並ぶことになっている。アセットマネジメントと言うと古臭いと感じるか、新しいと感じるかは読者の感覚で大きく異なっている。本書籍の特徴は、従来のアセットマネジメント関連書籍とは大きく異なった内容、特に、インフラ建設管理の主体である国や地方自治体における予算や公会計、議会制度や契約などに踏み込んで紹介、説明している。是非、書店に並んだ「アセットマネジメント・大全」を手に取って,気に入ったら購入してほしい。なお、当該書籍の表紙は、私が基本デザインをした青を基調とした自信作である。
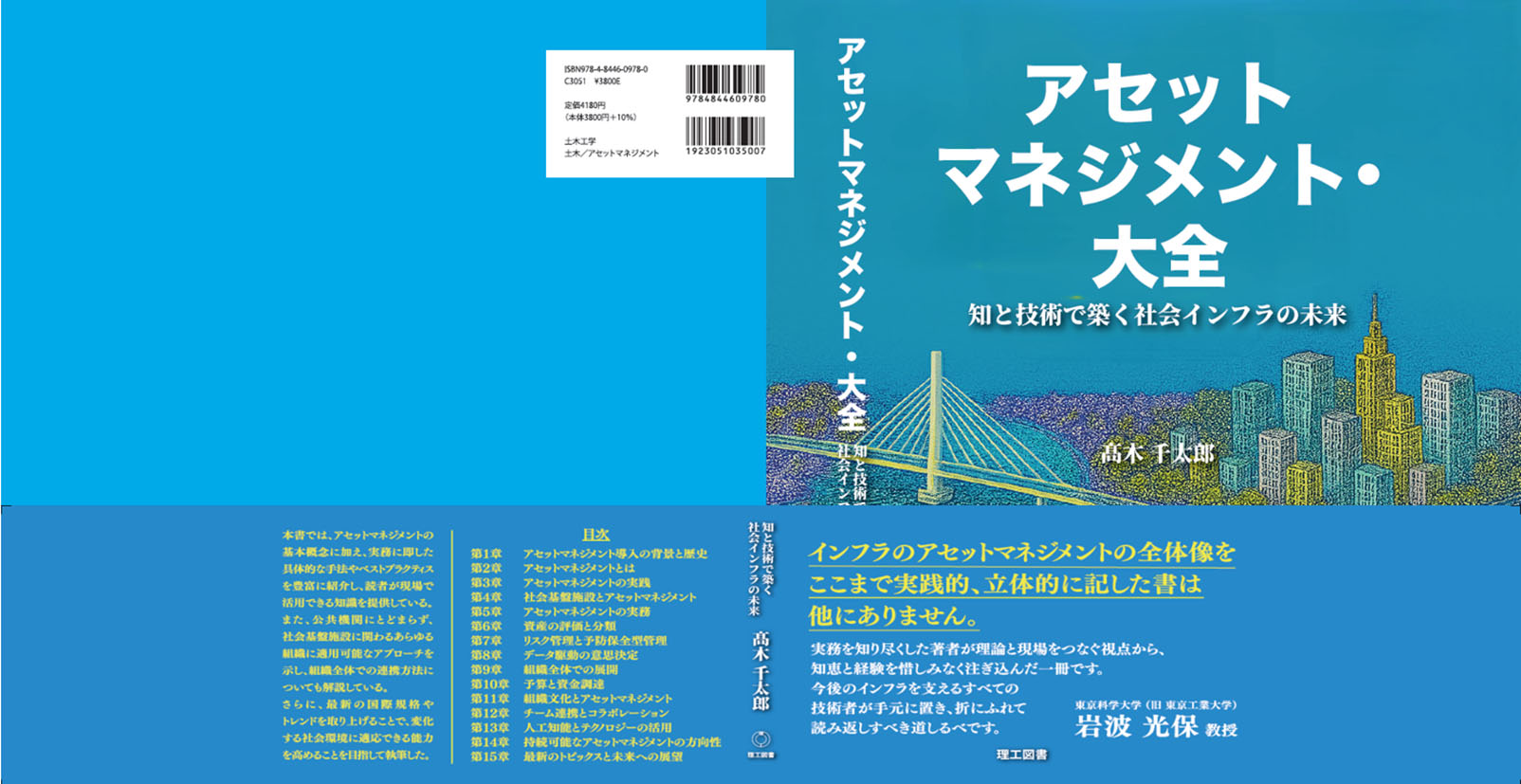
図‐10 アセットマネジメント・大全 ‐知と技術で築く社会インフラの未来
今回の連載の最後に、本稿を読まれた読者の皆様が、日々何気なく渡っている橋の背後にある技術と努力に思いを馳せ、社会基盤を守り続ける意義を再確認されることを願ってやまない。次回の連載の主題は、我が国の道路橋を対象とした設計基準「道路橋示方書・同解説」について、元道路橋示方書鋼橋編の幹事であった私の立場から、種々な課題、例えば、諸外国で使われない現状、ますますページ数が増え教科書化して使いにくくなった課題などについて論じる予定である。














 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら