新しい時代のインフラ・マネジメント考
5.受け身では守り切れない
社会インフラの維持管理において、多くの方々は「長寿命化、予防保全」と安易に言うが、はたして、それは実際に可能なのか? 実際に自治体の管理者として関わってきた者として、これを自治体で実行しようとすると、かなりハードルが高い。まずは、大きく先を阻むのは財政の問題がある。多くの自治体において、インフラの老朽化対策に、十分な予算確保は困難である。そのため、点検ですでに疲弊し、補修や補強・更新など、本来必要な行為が、なかなか実施できないのが実情である。つまり、老朽化対策の入り口で滞っている現実がある。また、点検さえしていれば、安全であるという誤った認識もある。さらに、人員の不足である。数も質も足りない。維持管理に一定程度の技術力、知識を有した職員がほとんど存在しない。民間企業においても、インフラに関するハード技術の技術者は思いのほか少ない。いや希少である。これまでの長年にわたる、建設事業の抑制政策で、実績と経験豊富な技術者は官民ともに少なくなってしまった。人材育成と言いながらも、実際にはほとんどできていない。そもそもが、官民ともに人材育成のために、何をやったらよいのかもわからないという現状もある。だから、教育もできていない。
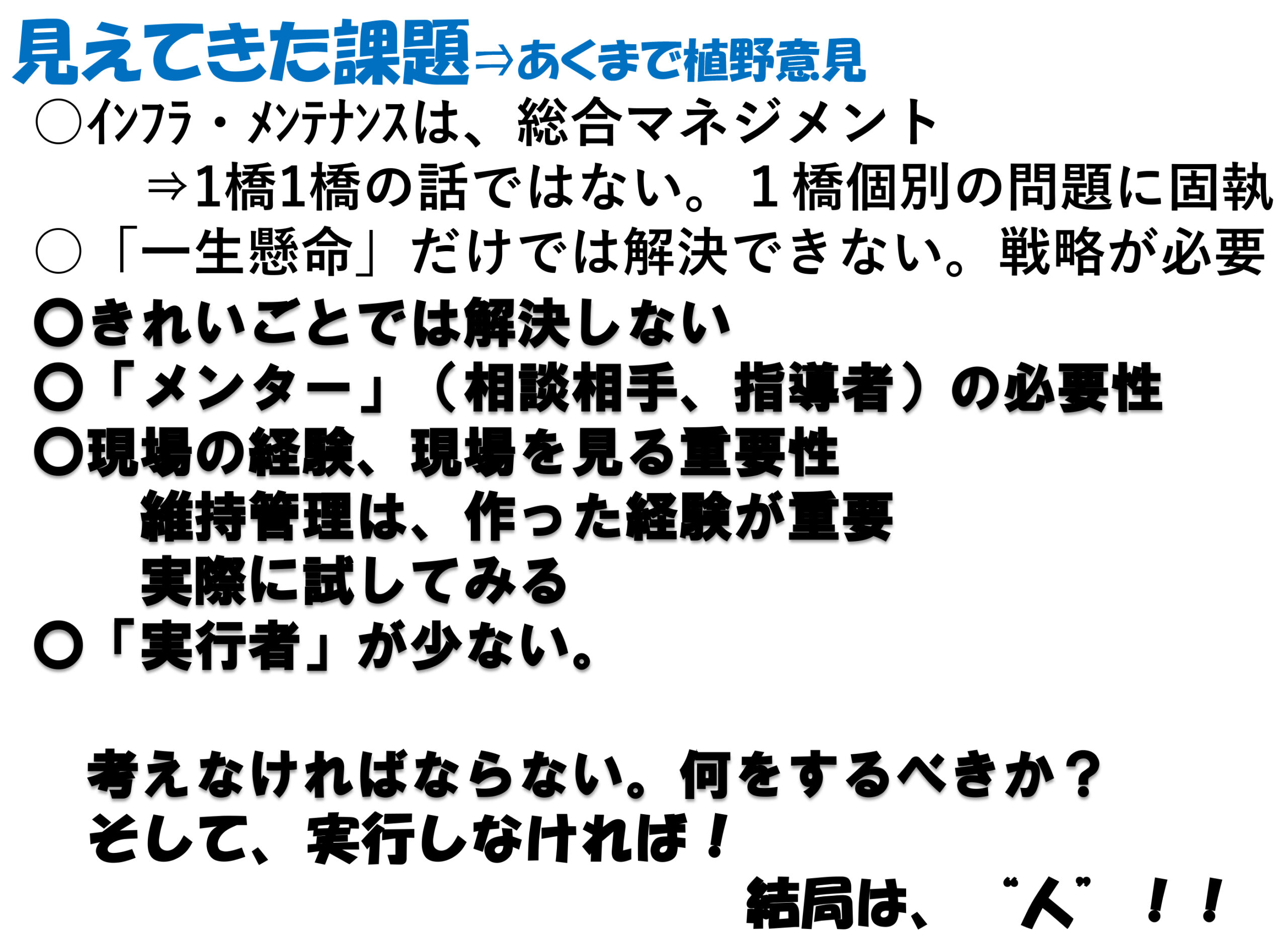
これまでの、「造る時代」では、1件1件の対応が主体であった。しかし管理する時代は、監理しているだけの全体多数を一気に視ていかねばならない。これがこれまでとは、大きな違いである。財政的にも技術的にも、単体の対応では追い付かなくなる。マネジメント力が必要になってくる。
社会インフラの点検の結果判定が、悪い物(Ⅲ評価)は、早急に補修をしなければならないことになっている。しかし、この補修という行為において、予想外のコストがかかる。のがわかっている。これで。現在多くの自治体では、補修が遅れている。この、補修材料や、補修工法の情報もあまりなく、経験も実績も少ない状況で、どうしたらよいのかという判断が非常に困難である。補修材料として、どういう物を使用していけばよいのかすら、わかっていないのが実情である。この、補修材料などの技術開発も、欧米に比べ遅れている。本来、この補修技術が維持管理の本丸であるが、補修・補強の技術の議論も足りないのである。ここが、おそらく今後の大きな課題となる。補修という行為を行って終わりではなく、公共物として、ある程度の耐久性を保たなければならない。実際に、安易に材料や工法を選定し、補修しても短期間で補修効果がなくなる、「再劣化」と言われる状況が実際に起きている。これも、当初は「存在しない」ということを言われた。嫌われても、さんざん伝えてきた。その結果、最近になってやっと認めていただけている。多くの方々は、補修補強さえすれば、元の状況に戻ると考えているがそうではない。本来もっと議論が必要な箇所である。こういった「維持管理技術の充実」「マネジメント力」が本来重要なのである。
6.まとめ
最近、良く言われるのが、「最近の人たち勉強してないね。」ということである。私も気になっている。学校の勉強ができた、とか、偏差値が良いと言う話ではなく、自分が何が必要でどう調べるか?という課題である。現在はインターネットで簡単に検索できる。ある程度のことは分かる。しかし、それを本気で願うならば、スペシャリストに聞くことだと思う。これがだれか?という問題もある。誰に聞けばよいのか、周りに居ない場合はどうすればよいのか?それは本人の工夫次第である。役割分担というものがある。それぞれの立場で考えることも異なる。やるべき音も異なる。これは、官・学・民で、それぞれ役割もやるべきことも違って当たり前だ。これを同じようにやろうとするからおかしなことになる。
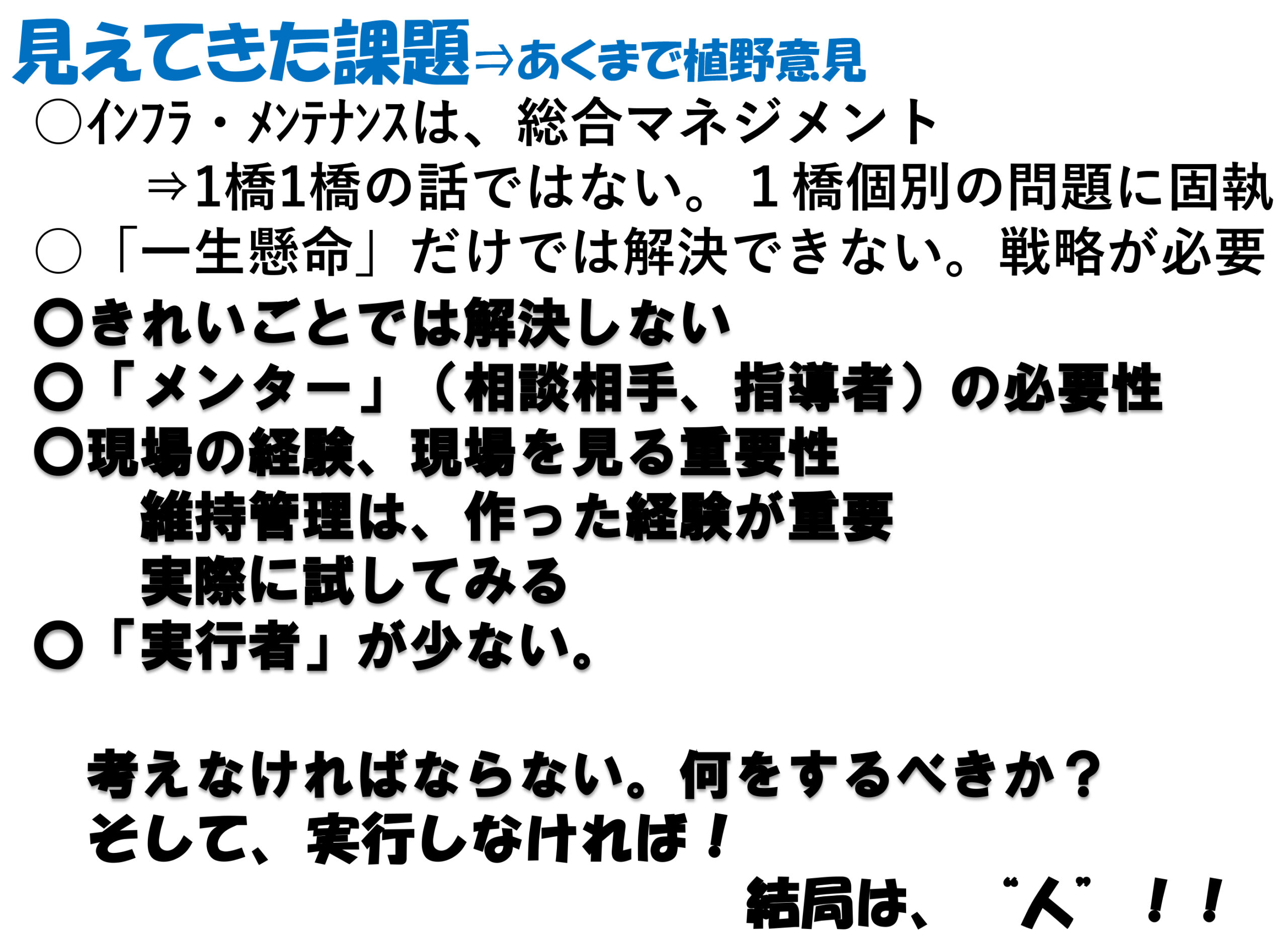
私は、実務者である。他分野のことにも興味はあるが、やるべきことは違う。これまで、特に橋梁に関して、幅広い知識と経験を積もうといろんなことをやってきた。システム開発や新技術、新事業、非破壊検査も学んだ。そして新たなマネジメントとしてインフラのPFI事業も経験見した。実務者にとって一番の勉強は、自分で経験することである。
「何かを学ぶために自分で体験する以上に良い方法はない。」というアインシュタインの言葉が座右の銘である。書物で読んだだけでは、なかなかわからない。実体験こそが、一番良いのだがなかなかそれも難しいので実際に体験した人に聞くのが一番であるはずである。政治家や、マスコミの言葉が薄っぺらいのは経験がないからである。これがわからない方々が多いのも事実。でそういう世の中でもある。情けないことである。
プロポーザルや総合評価で、実績を問うのもそういうことであるはずである。今の世の中、薄ぺらくなっている。現場で実際に見ることも重要である。
しかし、本来の勉強というのは、自分で決める物である。他人に言われて、決める物である。働き方も同じだと思う。今後、「群マネ」や「新技術導入」に関しては勉強が必要である。それはありきたりの勉強ではなく、「どうやって行くべきか?」なので、相談相手や聴ける相手を探したり、自分でとことん考えることが重要なのである。
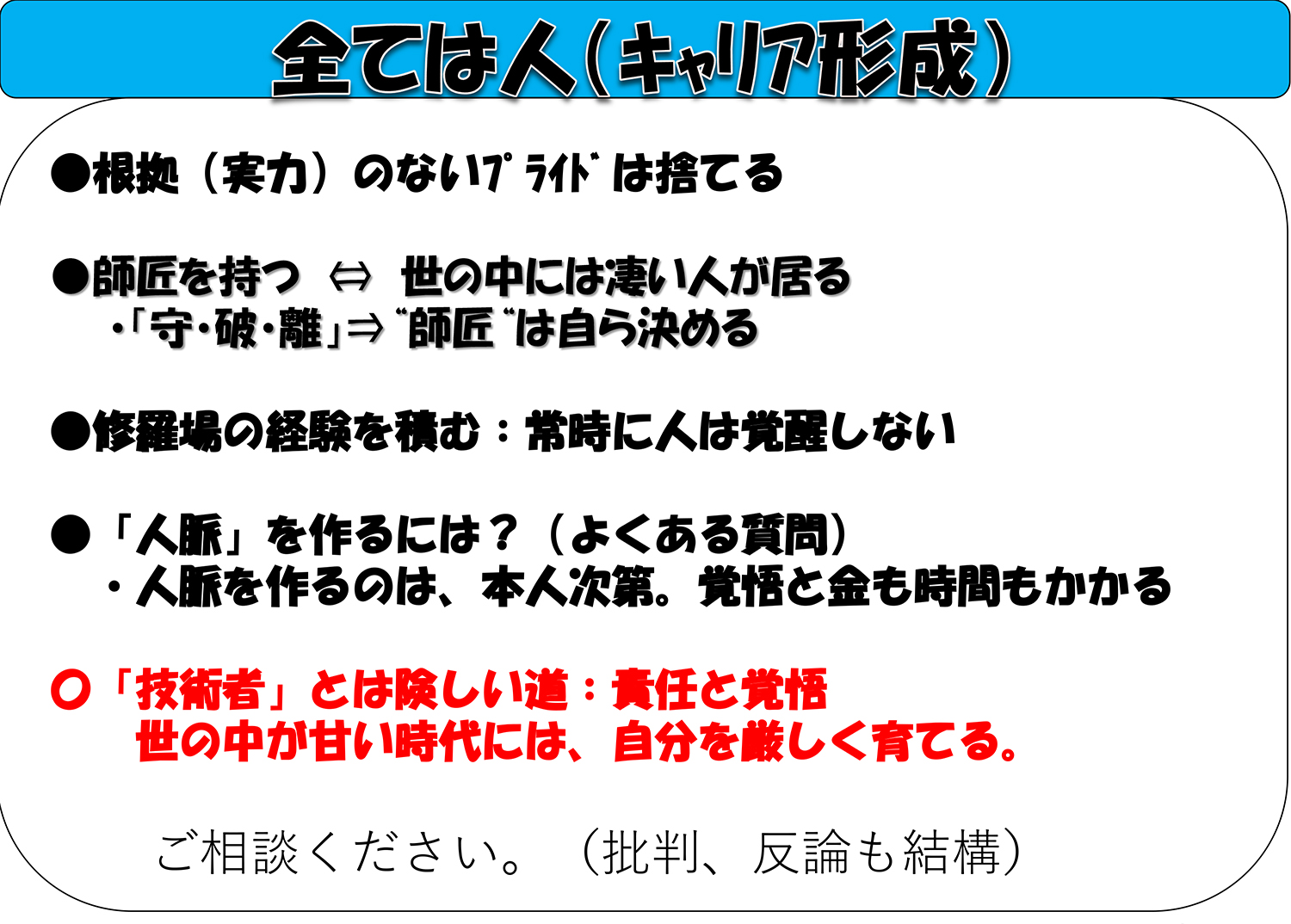


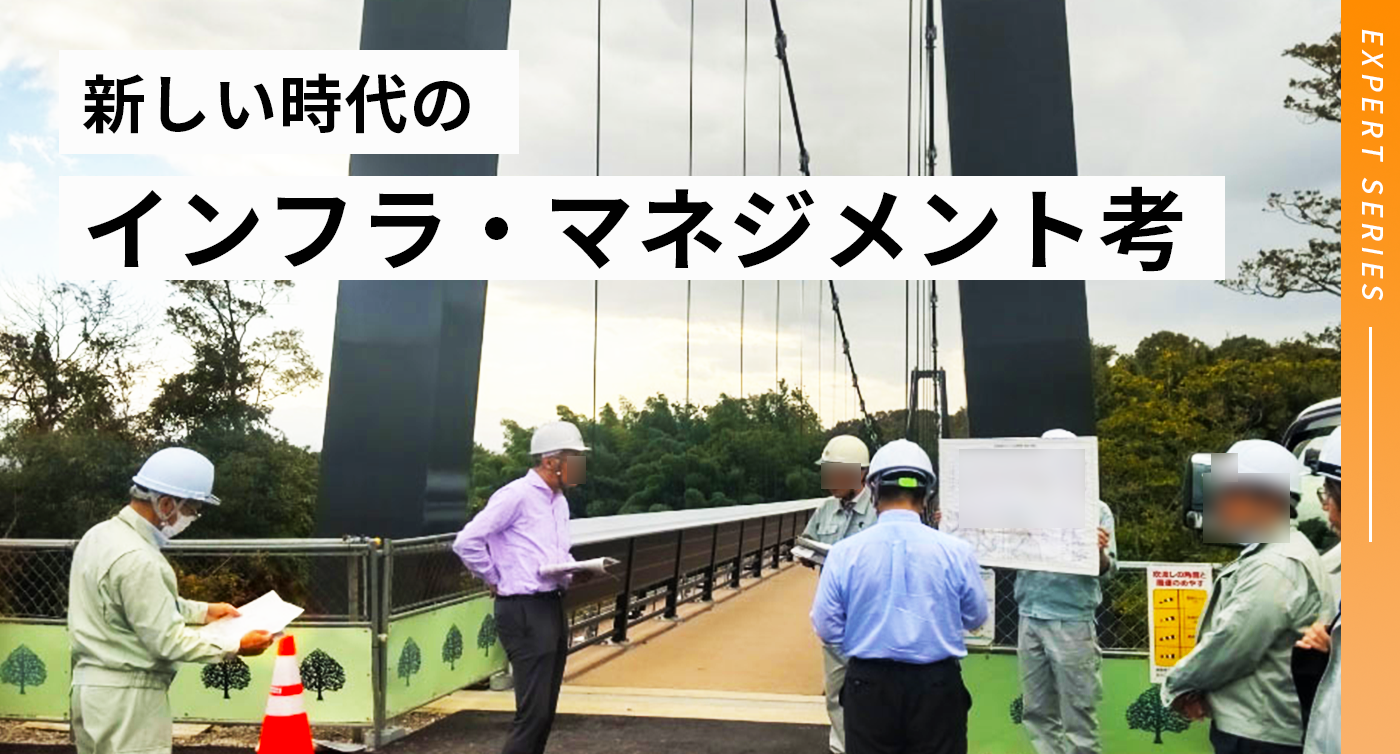











 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら