新しい時代のインフラ・マネジメント考
3.いつまで点検の話?
道路法の改定による、5年に一度の橋梁などの全数近接目視点検の義務化が施行されて10年3巡目に入った。今年度は点検要領の改訂が行われた。この中身は多くの方々の期待に反していたと言われている。特に実際に運用している管理者は、小規模橋梁や、健全性の良い物は点検が省略されると思っていたらしい。さらにボックスカルバートに関しても同様である。つまりは、構造物の健全性や重みによって点検の中身の緩和に期待したのであるようであるが、調書などかえって、手間が増える結果となったと言われている。
また、同時に点検コストの削減が問題になる中、逆に増加させなければならないのか?という意見もある。これは点検調書の作成に時間がかかるようになったからと言われているからである。まあ、しかし、これは当たり前のことである。点検しⅠからⅣまでの評価をすればよいわけではなく、そこに隠れている問題も、伝えなければ意味がない。なので、この点については、当たり前のことである。今までが中途半端だっただけである。

また、「新技術の導入」といいながら、さほどの新技術は、現れてこないというのは、私だけの意見だろうか?そして、新技術を導入すれば、コスト縮減になるとよく言われるが、私は逆ではないか?と考えている。かえって、コストは増加するはず。その理由は、
① 新技術を導入した場合、その信頼性の検証にかえって、時間と労力を必要とするはずである。
② 新技術の開発費用はどこから捻出するのか? 開発者にはその対価をどこから捻出するのか?開発者は、どう考えるのか? サービスか?
かつて、設計をシステム化した状況や、単純にはワープロが導入された時を考えればこれは分かるはず。特に①の検証は必ず必要となる。これは技術者としては当然である。未知のものを使えばそこに必ず発生する課題である。この検証ができない人たちがいるから新技術は進まない。新技術を導入しても、無駄になれば税金の無駄遣いなだけである。これを判断するにも知識と理解力が必要である。
結局、点検点検と言って、点検の目的を見失っている。点検することが目的になってしまっている。点検は維持管理の目的ではない。最初の確認作業である。1工程である。マネジメントを語る方々の多くも、1工程にとらわれすぎる。結局、何が目的なのかを見失っている。これが理解できないと、目的達成は無理である。途中の一工程で満足してしまっている。そろそろ、目的達成のための全体を見通し、全体を考えていきましょうよ。
どうすればよいかは、全体を通してのマネジメントが必要であるということである。
1工程だけを議論しても悩んでも始まらない。点検の後には修繕補修、その後には評価や監視そして更新計画など先行きは長い。費用もとんでもなくかかるはずである。
官庁の職員は、様々なことをトータルで判断し、運用なども工夫してほしいものである。
4.モニタリングシステムという例
この責任を実感させるための対処法として、富山では多くのモニタリングシステムを現場に導入し、監視している。現地に、いちいち行くのも大変だという理由もあるが、ある程度はデータで監視したいからである。しかし、我々は研究者ではないので、より実用的な、モニタリングシステムとしている。これを設置するときに、職員に対し注意しているのは、設置の目的である。何を監視したいのか?我々は研究者ではない。何がデータとして一番必要なのか?である。これによって、コストは下げられる。多くの場合業者や先生方の意見でつけてしまうと、よくわからないデータを取得することになり、設置しただけの自己満足になってしまい役に立たない。よくあるのが、コンサルなどの提案を真に受けてやると、「ひずみ」を測定するモニタリングシステムをつけたがる。おそらく彼ら自身が理解できていないのだと思うが、これを計測しても、職員は混乱するだけ。研究が目的ではないので、計測項目を例えばたわみに置き換えさせたり、ひび割れ幅そのものに絞らせている。こうすることによりコストダウンが図れる。


高級なモニタリングシステム(光ファイバー) / 安価なモニタリングシステムひび割れ幅検証装置
目的を絞れば、コストは下がる。
これは反論もあるだろうが、我々は実務者だからである。それを行うことによって効果を出さなければならず、なるべく安価に納めなければならない。「研究をさせてくれ」というのならば、それは別の話である。この辺が、世の中ごっちゃになっている。
決定者は、誇りとプライドを持つべきであり、その責任において実効あるべきである。同様に、よくモニタリングシステムで、議論になるのが「しきい値」という考え方であるが、こればかり言う方々は、やはり実態がわかっていない。しきい値は決めごとであり、構造物の解析などの結果から、出すが、その解析が行われなかったり理想的数字すぎては意味はない。やはりこれは決定事項なのである。実務者としてはそうではないはず。何が必要なのかは、確かに値は必要である。だから、決めればよいのだが、大体の場合、考えすぎて決められない。重要なのは「動き」「挙動」である。測定事項に何らかの異常が見られたら現地を確認し、対処するのが実務者。数値を追っていて気が付いたら崩落していたでは、笑い話にしかならなく、実務者としては目的を書く結果である。
モニタリングシステムは、新技術として大いに活用されるべきと思うが、現在においてもあまり聞かない。ドローンは新技術としても定着したが、これは点検においてある程度の効果を得たということなのだろう。その後、補修補強という話になるはずであるが、ここでコストがかかる。これが早急に実施できない場合、「監視という行為」が認められている。そこで、モニタリングシステムの有効性が出てくるはずなのだが?あまり議論されない。監視の一番、ポピュラーなのが目視で確認することである。これを行うにはいちいち現地まで出向かなければならない。なので、モニタリングシステムを設置し、情報を事務所まで飛ばす。
その後は技術者としての判断である。とにかく考えなければ進まない。
5.まとめ!
新年が明けた。さあ、この先どうしていくのか? 考えるべき時期である。特に官庁の職員は、責任を持って考えるべきである。富山では課長連中を脅していた「うまくすれば定年まで逃げ切れるかもしれない。しかし、インフラで下手をすると責任を取らされる世代になりかねないことを肝に銘じておけ。定年まで枕を高く寝られ、無事退職金を手にするには、やるべきことをきちんとやることだ。」と。何かあれば公務員には責任がある。それだけの責任があるということは他人事ではない。私も現役時には3億円の個人賠償保険に加入していた。公務員は個人が訴えられる場合も多い。これは民間の技術者も同じである。一定の責任はあるはず。しかし責任だけを押し付けるのではなく、技術者としての権威も持たせなければ片手落ちである。働き方改革と言ってはいるが私は、技術者の権限や地位を上げてあげるべきだと考えている。つまり、本来はそれぞれの「地位改革」が必要なのだ。
大切なのは何が目的か? ということである。これが理解できなければ新技術も何を導入したらよいのかわからないだろう。はっきり年始にあたり言っておくと、地方などを回ってみても東京で会議に出ても官も民もみなさん、勉強していない。勉強というのは机に座って、マニュアルを読むことではなく、「自分で考えること」である。目的達成のために、何をすればよいのか? 世の中はどう動いているのか? 世の中にはどういう技術があるのか? 世の中にはどういう人が先進的にやっているのか? ということを情報収集し考えることが勉強である。そして、仕事の師匠や、相談できる人間を作ることである。
どうも最近、官も民も現場での経験を軽視する傾向にあるように感じてならない。ネクタイを締めスーツを着た人間が何でもわかっているか? というとそうではない。先に書いたが「データ、データ」と言って、無駄なデータを集めても、何も解決はしない。集めるデータも何が必要なのか考えてやらないと結果は出ない。
物を見極める力ができてこそ、初めて、一人前であるがそうでもない人間が、うわべの話をしている。そしてこれに惑わされる人間もいる。これは一概に経験年数ではないが、少ない経験年数で極めるのは無理である。直観で一目見ただけでその橋の異常を感じられるようになれば、点検もスムーズにいきコストダウンにもつながる。そういう人間が各所に居れば問題は解決する。そして、「群マネ」も「新技術導入」も目的は一緒。これがなかなか、すすまないのが不思議である。実は、やる気がないのか? やられると困るのか? である。
しかし、責任は自分たちにふりかかる。お気をつけて。
(次回は2月16日に掲載予定です)


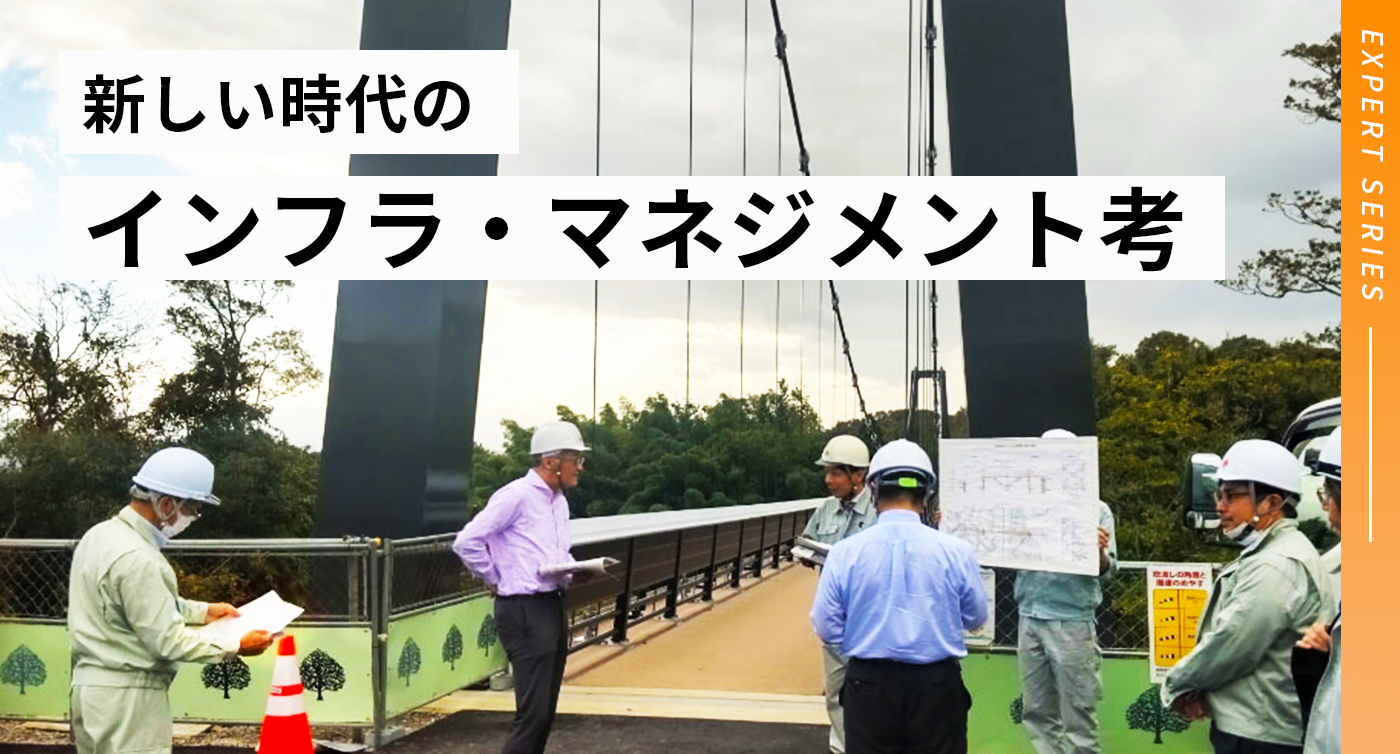




.jpg)






 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら