NEWSNEWS List
2025.03.19
A-Forum 第53回AFフォーラム「構造美について―合理性と倫理性の視点から―」を開催
アーキニアリング・デザインフォーラム(Archi‐Neering Design Forum 略称 A-Forum・斎藤公男代表)は昨秋にA-Forum(東京都千代田区)内で第53回AFフォーラム「構造美について―合理性と倫理性の視点から―」を対面と配信で開催した。
アーキニアリング・デザイン(以下AND)とは、ArchitectureとEngineering Designとの融合・触発・統合の様相を意味する言葉。このANDの基本理念は、technology (科学・工学・技術)のもつ役割や可能性を見据え、より良き「建築」の創出を目指すことにある。A‐Forumは、このANDの理念の実現と構造設計・構造デザインに関心を抱く人たちに、積極的かつ自由に活用してもらうための「集いの場(フォーラム)」となることを目的としており、フォーラムが建築の研究・教育・設計・生産に関わる人々の相互交流を通じて、次世代の建築界に新しい活力を生み出すための一助になるために活動している。A-Forumが発足した数々の研究会がテーマを設けて不定期で意見交換会を行っている。今回行われたAFフォーラムもその一つで「構造美について―合理性と倫理性の視点から―」をテーマに八馬智氏(千葉工業大学)、名和研二氏(すわ製作所・なわけんジム)、中畠敦広氏(yAt構造設計事務所)の3名のパネリストが講演した。
 はじめにコーディネーターの神田順氏(写真左)が「ひたすら合理的で無駄のない形を美しいといえるか。美しくすることで倫理性に外れることはないか。合理的であるべきとする所に倫理性を感じるか。全体のバランスが大切だとして、そこに形態としての美しさを組み込むために、構造合理性から少し離れるときの決断をどのようにするかは設計者個人の技のように思われる。ここでは構造設計者あるいは構造エンジニアから構造を美しくしようと思うか、あるいは構造を美しいと思うのはどんな時かという問いかけへの対応を聞いてみたい」と挨拶した。
はじめにコーディネーターの神田順氏(写真左)が「ひたすら合理的で無駄のない形を美しいといえるか。美しくすることで倫理性に外れることはないか。合理的であるべきとする所に倫理性を感じるか。全体のバランスが大切だとして、そこに形態としての美しさを組み込むために、構造合理性から少し離れるときの決断をどのようにするかは設計者個人の技のように思われる。ここでは構造設計者あるいは構造エンジニアから構造を美しくしようと思うか、あるいは構造を美しいと思うのはどんな時かという問いかけへの対応を聞いてみたい」と挨拶した。
橋のデザイン 八馬智氏(千葉工業大学)
 八馬氏(写真右)は今回土木に携わる立場からの登壇となる。土木や橋に対する思いや物の見方をライフワーク的に考えるという「都市鑑賞者」であり、元プロの「ドボクマニア」であるという自己紹介から始まり、「橋のデザイン」と題し、自身の携わった橋や魅力的な国内外の橋を紹介した。
八馬氏(写真右)は今回土木に携わる立場からの登壇となる。土木や橋に対する思いや物の見方をライフワーク的に考えるという「都市鑑賞者」であり、元プロの「ドボクマニア」であるという自己紹介から始まり、「橋のデザイン」と題し、自身の携わった橋や魅力的な国内外の橋を紹介した。
大学時代、工業デザインを学んだが、バブル期の消費を促すためのデザインに疑問を感じていた。とあるきっかけから「橋がデザインの対象になる」ということを知り、土木に魅力を感じるようになり、設計コンサルタントに就職したという。はじめて携わった室蘭・白鳥大橋や予備設計の頃から苦労してデザインした鋼箱桁の旭川・金星橋、特殊なジャケット式の橋脚、桁のおさまりの部分をエンジニアと工夫した室蘭・追直漁港沖合⼈⼯島連絡橋、橋桁が盛土の部分に刺さったデザインで国道の走行車両から見て圧迫感のない形を工夫した上川・大雪大橋は「一瞬で通りすぎるので誰も見てくれない。しかし、誰も見てくれないところが『土木の面白いところ』なのでは」と述べた。このほか、タワーを建ててやじろべえの腕を伸ばすようにする施工性から生まれた形式である鶴見つばさ橋や一般的な橋とは異なる形式を持つゲートブリッジ、当時スペインが内戦中だったため、ミニマムを追求したトロハのアリオスの水路橋、登場以前以降では世界の橋梁の傾向が変わるきっかけとなったカラトラバのデザインした橋など独自の視点で国内外の著名な橋梁の魅力をわかりやすく紹介した。
また、「橋はなにと戦っているのか」という切り口から、構造的要因、環境的要因、社会的要因の3つをあげた。構造的な要因に関しては、荷重の条件が形に立ち上ってくること、さらに材料をどう捉えていくかが重要である。環境的な要因に関しては地形地質や基礎をどうするかというバランスなどが複雑にパラメーターとして絡んでくる上、環境保全や経年変化を考えなくてはならない。社会的要因に関しては、全体を支配するコストが挙げられる。税金を使って建てられるため、コストミニマムで考えなくてはならず、前例主義的な面もある。公共なので政治的な観点や景観も重要である。
さらに押さえておくべき、橋の特性についても言及。建築と比較し、サイズが大きい、寿命が長い、公共性が高いという3点をあげた。このような理由から構造が卓越した姿になり、風景として構成される。文化や社会は反映されるが、建築と大きく違うのは設計者個人の主義主張は性質として反映されにくいと述べた。また、現代の橋のデザインの肝となると思うことは「さまざまな設計要件のバランスを取りつつ、ノイズを減らして構造フォルムを引き立てる」と述べ、ビリントンの書籍「塔と橋 構造芸術の誕生」(鹿島出版会 (2001/8/10))から3Eと呼ばれる項目を紹介。Efficiency(効率性)、Economy(経済性)、Elegance(優美さ)の3つを意識しながらデザインをすることがこれから重要ではないかと説明した。
最後に橋が戦う相手はさらに複雑になっていると述べ、示方書を満足するだけでは不十分でなにを実現するために技術を使うのかということを現代は突きつけられていると締めくくった。
−拾う(ひろう)て広う(ひろう)構造デザイン活動−(惑った)WandeR・ワンダー・WandeR(いささかすばらしき)ストラクチャーであること「惑った構造がだきつく先」 名和研二氏(すわ製作所・なわけんジム)
 名和氏は冒頭で、惑った(wAnder)(単独では優位性・効果の高くない状態)だきつくこと(wOnder)(複合として優位性・効果の高い状態)と自身の定義を説明し、個の要素を「結びつけるもの」が構造だと思っており、そのことにより、個々である以上の魅力(意味、効果、結果)を持つことができたものが構造美なのではと思っていると述べた。その定義をもとにテトラポットを作る時にできた廃コンクリートブロックを積み上げて建築された憩いの場である「潜水士のためのグラスハウス」や業者の介入を最小限でとどめながら建築家自身がセルフビルドした40mm鉄板床をRCの耐力壁とφ60mmの丸鋼柱で支持した歯科医院「空飛ぶジュータン」などの自身が構造を手がけた建築を紹介した。名和氏は、「ある条件が時間の中で釣り合った状態を美しいと呼ぶのでは」と言い表し、個の一つひとつの要素は儚いものであるが、そこには優劣というものは本来なく、重なった時にパワーと所作が合い、達成できた時には美しいと思えると述べた。
名和氏は冒頭で、惑った(wAnder)(単独では優位性・効果の高くない状態)だきつくこと(wOnder)(複合として優位性・効果の高い状態)と自身の定義を説明し、個の要素を「結びつけるもの」が構造だと思っており、そのことにより、個々である以上の魅力(意味、効果、結果)を持つことができたものが構造美なのではと思っていると述べた。その定義をもとにテトラポットを作る時にできた廃コンクリートブロックを積み上げて建築された憩いの場である「潜水士のためのグラスハウス」や業者の介入を最小限でとどめながら建築家自身がセルフビルドした40mm鉄板床をRCの耐力壁とφ60mmの丸鋼柱で支持した歯科医院「空飛ぶジュータン」などの自身が構造を手がけた建築を紹介した。名和氏は、「ある条件が時間の中で釣り合った状態を美しいと呼ぶのでは」と言い表し、個の一つひとつの要素は儚いものであるが、そこには優劣というものは本来なく、重なった時にパワーと所作が合い、達成できた時には美しいと思えると述べた。
構造美への探究 中畠敦広氏(yAt構造設計事務所)
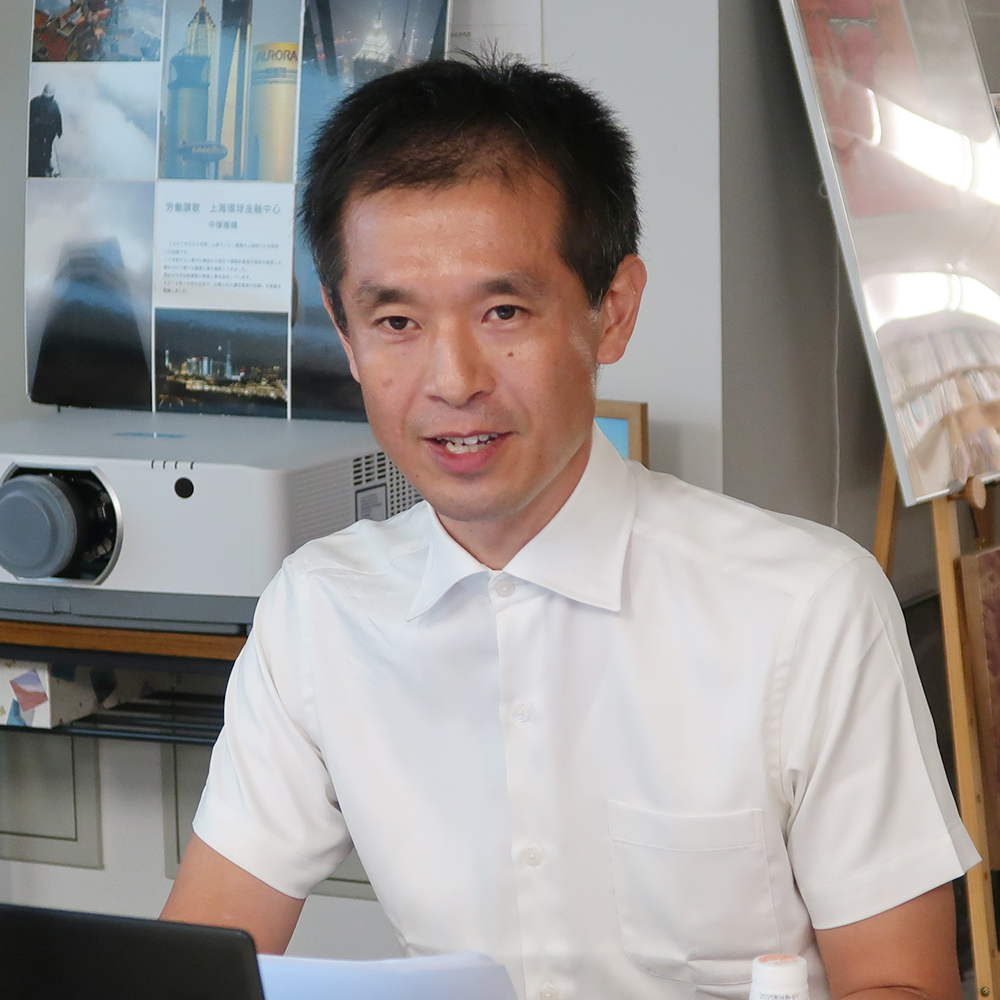 中畠氏(写真右)は「構造美への探究」と題し、就職してすぐに起こった耐震偽装事件から強く感じた構造設計者の職業倫理や自身の構造設計スタンス、構造の美しさ自体について考えさられた「認定こども園こどものにわ西浦和幼稚園」等のプロジェクトを紹介した。
中畠氏(写真右)は「構造美への探究」と題し、就職してすぐに起こった耐震偽装事件から強く感じた構造設計者の職業倫理や自身の構造設計スタンス、構造の美しさ自体について考えさられた「認定こども園こどものにわ西浦和幼稚園」等のプロジェクトを紹介した。
師である構造家の新谷眞人氏から言われた「美しくない構造は力学的に合理的ではない」という言葉から「美しい構造は力学的に合理的であるのか」、「構造における美しさとはなんなのか」、「構造は美しくあるべきか」、「美しさを評価するのは誰か」ということを考えはじめ、今もまだ答えが出ておらず、まさしくこの問いというのは今回のフォーラムのテーマにかかるのではと述べた。答えを模索する日々だが、木村俊彦氏の著書「構造設計とは」( 鹿島出版会 (1991/12/1))で記されている構造の美とは「ある時には強く激しく、ある時にはやさしく人の心に働きかけ、人の心に力と運動と安らぎを生ぜしめるエネルギーの呼称である」という定義は非常に難しいが、一方で美というのは表面的な外的な美と本質的な美があり、一時的な美と持続的な美がある。前者はわかりやすく一時的に商品価値が高いものを指し、後者は構造の美しさだと書かれており、これが自身ではしっくりくる言葉であり、先ほど述べた問いへのヒントのように感じたと語った。
パネリストの発表の後は質疑応答が行われ、活発な議論が繰り広げられた。

−−催しの後、A-Forum代表の斎藤氏(写真右)にコメントをいただいた
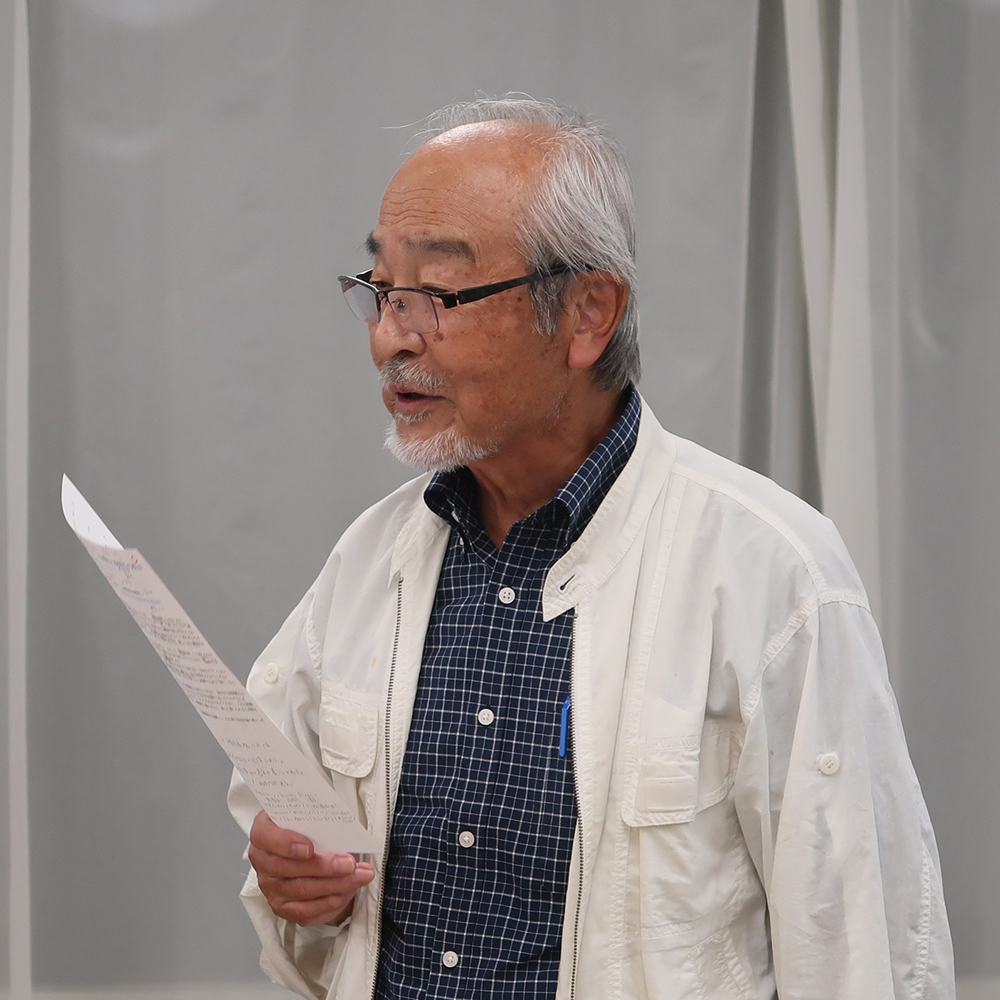 10年前に橋と建築の距離を縮めたいと考え、セミナーをA-Forumで行いました。その時にすごく面白かったので、またなにか展開できないかと1年前に建築ジャーナルで「美しい橋」という企画を八馬先生と渡邉竜一さん(ネイ&パートナーズジャパン)と作りました。建築と橋梁という別のフィールドの者同士の議論が噛み合った一つの土壌を作れたことはとても大きかったと思っています。また、八馬先生の著書である「橋をデザインする」(共著・技報堂出版 (2023/3/14))の中で推薦図書に私の「空間 構造 物語〜ストラクチュラル・デザインのゆくえ」( 彰国社 (2003/10/1))を挙げていただき、その解説には「著者は構造家だが学ぶべき橋の古典のほぼすべてが登場する。橋梁学徒必読の建築構造本である」と紹介してくださり、橋と建築が一体であるという私の考えがこの一文に凝縮されていてとても嬉しく思いました。さて、今回のテーマですが、構造美に関していうと橋は「元祖」であると考えます。私が一番好きな橋であるスイスのサルギナトーベル橋は、たった一つの集落に行くため深い谷を越える橋であり、風景の中にきれいになじんで宝石のように存在し、自然の景観の中に橋がどうデザインされるべきか問いかけている。これはまさに構造美だと思います。今回のフォーラムで非常に面白く感じたのは構造美とは「構造の美」なのか、または「構造と美」なのかというところを考えさせられました。パリのエッフェル塔は今ではなくてはならないシンボルですが、建築された当時はたくさんの意匠設計者たちが反対していました。芸術家には構造美はわからないのか? それは今の時代でも同じです。人によって違うし、時代によっても違う。構造美とは不変的なものだと思うのですが、そう思うと古典を学ぶということはとても大切だと思います。今後、AIなどの時代になってますますこのような議論が必要になってくると思います。
10年前に橋と建築の距離を縮めたいと考え、セミナーをA-Forumで行いました。その時にすごく面白かったので、またなにか展開できないかと1年前に建築ジャーナルで「美しい橋」という企画を八馬先生と渡邉竜一さん(ネイ&パートナーズジャパン)と作りました。建築と橋梁という別のフィールドの者同士の議論が噛み合った一つの土壌を作れたことはとても大きかったと思っています。また、八馬先生の著書である「橋をデザインする」(共著・技報堂出版 (2023/3/14))の中で推薦図書に私の「空間 構造 物語〜ストラクチュラル・デザインのゆくえ」( 彰国社 (2003/10/1))を挙げていただき、その解説には「著者は構造家だが学ぶべき橋の古典のほぼすべてが登場する。橋梁学徒必読の建築構造本である」と紹介してくださり、橋と建築が一体であるという私の考えがこの一文に凝縮されていてとても嬉しく思いました。さて、今回のテーマですが、構造美に関していうと橋は「元祖」であると考えます。私が一番好きな橋であるスイスのサルギナトーベル橋は、たった一つの集落に行くため深い谷を越える橋であり、風景の中にきれいになじんで宝石のように存在し、自然の景観の中に橋がどうデザインされるべきか問いかけている。これはまさに構造美だと思います。今回のフォーラムで非常に面白く感じたのは構造美とは「構造の美」なのか、または「構造と美」なのかというところを考えさせられました。パリのエッフェル塔は今ではなくてはならないシンボルですが、建築された当時はたくさんの意匠設計者たちが反対していました。芸術家には構造美はわからないのか? それは今の時代でも同じです。人によって違うし、時代によっても違う。構造美とは不変的なものだと思うのですが、そう思うと古典を学ぶということはとても大切だと思います。今後、AIなどの時代になってますますこのような議論が必要になってくると思います。
当日の模様はA-ForumのYouTubeチャンネルでも視聴できる。https://youtu.be/6z05XfZWlAA
アーキニアリング・デザイン(以下AND)とは、ArchitectureとEngineering Designとの融合・触発・統合の様相を意味する言葉。このANDの基本理念は、technology (科学・工学・技術)のもつ役割や可能性を見据え、より良き「建築」の創出を目指すことにある。A‐Forumは、このANDの理念の実現と構造設計・構造デザインに関心を抱く人たちに、積極的かつ自由に活用してもらうための「集いの場(フォーラム)」となることを目的としており、フォーラムが建築の研究・教育・設計・生産に関わる人々の相互交流を通じて、次世代の建築界に新しい活力を生み出すための一助になるために活動している。A-Forumが発足した数々の研究会がテーマを設けて不定期で意見交換会を行っている。今回行われたAFフォーラムもその一つで「構造美について―合理性と倫理性の視点から―」をテーマに八馬智氏(千葉工業大学)、名和研二氏(すわ製作所・なわけんジム)、中畠敦広氏(yAt構造設計事務所)の3名のパネリストが講演した。
 はじめにコーディネーターの神田順氏(写真左)が「ひたすら合理的で無駄のない形を美しいといえるか。美しくすることで倫理性に外れることはないか。合理的であるべきとする所に倫理性を感じるか。全体のバランスが大切だとして、そこに形態としての美しさを組み込むために、構造合理性から少し離れるときの決断をどのようにするかは設計者個人の技のように思われる。ここでは構造設計者あるいは構造エンジニアから構造を美しくしようと思うか、あるいは構造を美しいと思うのはどんな時かという問いかけへの対応を聞いてみたい」と挨拶した。
はじめにコーディネーターの神田順氏(写真左)が「ひたすら合理的で無駄のない形を美しいといえるか。美しくすることで倫理性に外れることはないか。合理的であるべきとする所に倫理性を感じるか。全体のバランスが大切だとして、そこに形態としての美しさを組み込むために、構造合理性から少し離れるときの決断をどのようにするかは設計者個人の技のように思われる。ここでは構造設計者あるいは構造エンジニアから構造を美しくしようと思うか、あるいは構造を美しいと思うのはどんな時かという問いかけへの対応を聞いてみたい」と挨拶した。橋のデザイン 八馬智氏(千葉工業大学)
 八馬氏(写真右)は今回土木に携わる立場からの登壇となる。土木や橋に対する思いや物の見方をライフワーク的に考えるという「都市鑑賞者」であり、元プロの「ドボクマニア」であるという自己紹介から始まり、「橋のデザイン」と題し、自身の携わった橋や魅力的な国内外の橋を紹介した。
八馬氏(写真右)は今回土木に携わる立場からの登壇となる。土木や橋に対する思いや物の見方をライフワーク的に考えるという「都市鑑賞者」であり、元プロの「ドボクマニア」であるという自己紹介から始まり、「橋のデザイン」と題し、自身の携わった橋や魅力的な国内外の橋を紹介した。大学時代、工業デザインを学んだが、バブル期の消費を促すためのデザインに疑問を感じていた。とあるきっかけから「橋がデザインの対象になる」ということを知り、土木に魅力を感じるようになり、設計コンサルタントに就職したという。はじめて携わった室蘭・白鳥大橋や予備設計の頃から苦労してデザインした鋼箱桁の旭川・金星橋、特殊なジャケット式の橋脚、桁のおさまりの部分をエンジニアと工夫した室蘭・追直漁港沖合⼈⼯島連絡橋、橋桁が盛土の部分に刺さったデザインで国道の走行車両から見て圧迫感のない形を工夫した上川・大雪大橋は「一瞬で通りすぎるので誰も見てくれない。しかし、誰も見てくれないところが『土木の面白いところ』なのでは」と述べた。このほか、タワーを建ててやじろべえの腕を伸ばすようにする施工性から生まれた形式である鶴見つばさ橋や一般的な橋とは異なる形式を持つゲートブリッジ、当時スペインが内戦中だったため、ミニマムを追求したトロハのアリオスの水路橋、登場以前以降では世界の橋梁の傾向が変わるきっかけとなったカラトラバのデザインした橋など独自の視点で国内外の著名な橋梁の魅力をわかりやすく紹介した。
 八馬氏が設計に携わった橋
八馬氏が設計に携わった橋
 国内外の魅力的な橋
国内外の魅力的な橋
また、「橋はなにと戦っているのか」という切り口から、構造的要因、環境的要因、社会的要因の3つをあげた。構造的な要因に関しては、荷重の条件が形に立ち上ってくること、さらに材料をどう捉えていくかが重要である。環境的な要因に関しては地形地質や基礎をどうするかというバランスなどが複雑にパラメーターとして絡んでくる上、環境保全や経年変化を考えなくてはならない。社会的要因に関しては、全体を支配するコストが挙げられる。税金を使って建てられるため、コストミニマムで考えなくてはならず、前例主義的な面もある。公共なので政治的な観点や景観も重要である。
さらに押さえておくべき、橋の特性についても言及。建築と比較し、サイズが大きい、寿命が長い、公共性が高いという3点をあげた。このような理由から構造が卓越した姿になり、風景として構成される。文化や社会は反映されるが、建築と大きく違うのは設計者個人の主義主張は性質として反映されにくいと述べた。また、現代の橋のデザインの肝となると思うことは「さまざまな設計要件のバランスを取りつつ、ノイズを減らして構造フォルムを引き立てる」と述べ、ビリントンの書籍「塔と橋 構造芸術の誕生」(鹿島出版会 (2001/8/10))から3Eと呼ばれる項目を紹介。Efficiency(効率性)、Economy(経済性)、Elegance(優美さ)の3つを意識しながらデザインをすることがこれから重要ではないかと説明した。
最後に橋が戦う相手はさらに複雑になっていると述べ、示方書を満足するだけでは不十分でなにを実現するために技術を使うのかということを現代は突きつけられていると締めくくった。
−拾う(ひろう)て広う(ひろう)構造デザイン活動−(惑った)WandeR・ワンダー・WandeR(いささかすばらしき)ストラクチャーであること「惑った構造がだきつく先」 名和研二氏(すわ製作所・なわけんジム)
 名和氏は冒頭で、惑った(wAnder)(単独では優位性・効果の高くない状態)だきつくこと(wOnder)(複合として優位性・効果の高い状態)と自身の定義を説明し、個の要素を「結びつけるもの」が構造だと思っており、そのことにより、個々である以上の魅力(意味、効果、結果)を持つことができたものが構造美なのではと思っていると述べた。その定義をもとにテトラポットを作る時にできた廃コンクリートブロックを積み上げて建築された憩いの場である「潜水士のためのグラスハウス」や業者の介入を最小限でとどめながら建築家自身がセルフビルドした40mm鉄板床をRCの耐力壁とφ60mmの丸鋼柱で支持した歯科医院「空飛ぶジュータン」などの自身が構造を手がけた建築を紹介した。名和氏は、「ある条件が時間の中で釣り合った状態を美しいと呼ぶのでは」と言い表し、個の一つひとつの要素は儚いものであるが、そこには優劣というものは本来なく、重なった時にパワーと所作が合い、達成できた時には美しいと思えると述べた。
名和氏は冒頭で、惑った(wAnder)(単独では優位性・効果の高くない状態)だきつくこと(wOnder)(複合として優位性・効果の高い状態)と自身の定義を説明し、個の要素を「結びつけるもの」が構造だと思っており、そのことにより、個々である以上の魅力(意味、効果、結果)を持つことができたものが構造美なのではと思っていると述べた。その定義をもとにテトラポットを作る時にできた廃コンクリートブロックを積み上げて建築された憩いの場である「潜水士のためのグラスハウス」や業者の介入を最小限でとどめながら建築家自身がセルフビルドした40mm鉄板床をRCの耐力壁とφ60mmの丸鋼柱で支持した歯科医院「空飛ぶジュータン」などの自身が構造を手がけた建築を紹介した。名和氏は、「ある条件が時間の中で釣り合った状態を美しいと呼ぶのでは」と言い表し、個の一つひとつの要素は儚いものであるが、そこには優劣というものは本来なく、重なった時にパワーと所作が合い、達成できた時には美しいと思えると述べた。 潜水士のためのグラスハウス
潜水士のためのグラスハウス
構造美への探究 中畠敦広氏(yAt構造設計事務所)
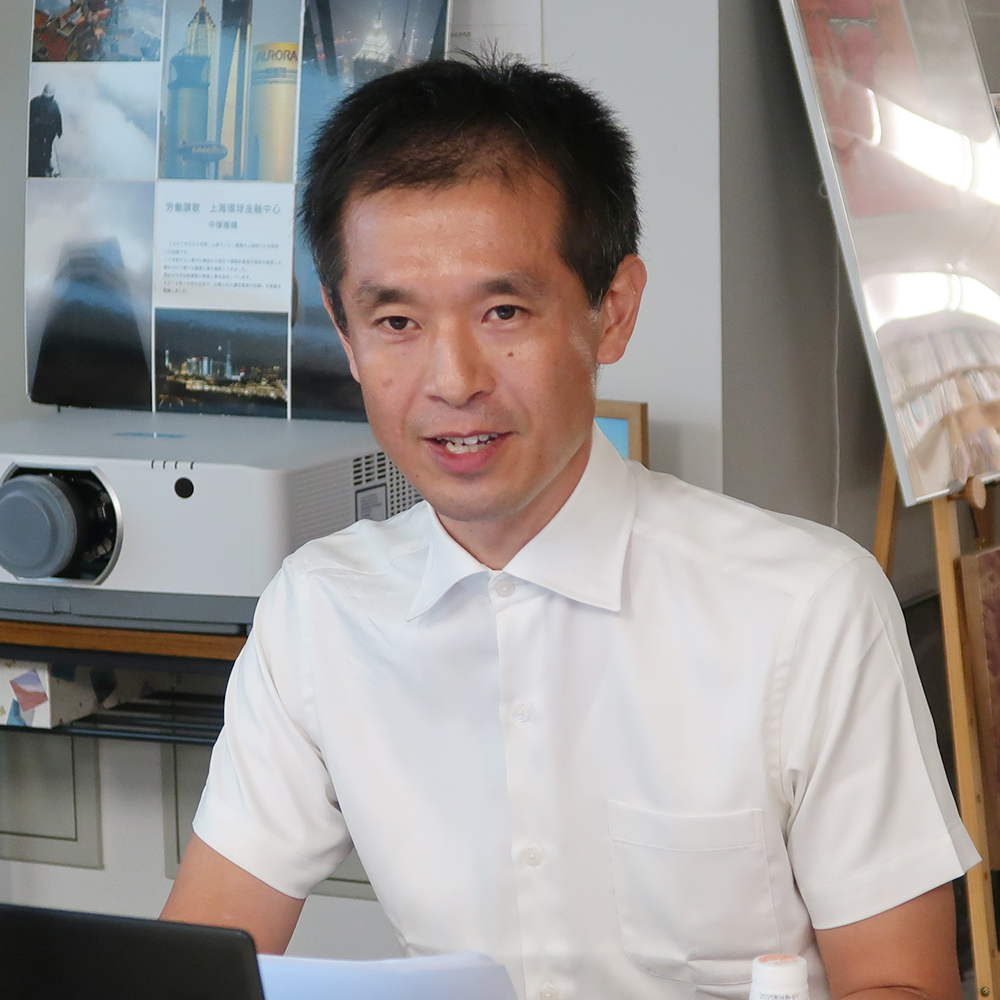 中畠氏(写真右)は「構造美への探究」と題し、就職してすぐに起こった耐震偽装事件から強く感じた構造設計者の職業倫理や自身の構造設計スタンス、構造の美しさ自体について考えさられた「認定こども園こどものにわ西浦和幼稚園」等のプロジェクトを紹介した。
中畠氏(写真右)は「構造美への探究」と題し、就職してすぐに起こった耐震偽装事件から強く感じた構造設計者の職業倫理や自身の構造設計スタンス、構造の美しさ自体について考えさられた「認定こども園こどものにわ西浦和幼稚園」等のプロジェクトを紹介した。師である構造家の新谷眞人氏から言われた「美しくない構造は力学的に合理的ではない」という言葉から「美しい構造は力学的に合理的であるのか」、「構造における美しさとはなんなのか」、「構造は美しくあるべきか」、「美しさを評価するのは誰か」ということを考えはじめ、今もまだ答えが出ておらず、まさしくこの問いというのは今回のフォーラムのテーマにかかるのではと述べた。答えを模索する日々だが、木村俊彦氏の著書「構造設計とは」( 鹿島出版会 (1991/12/1))で記されている構造の美とは「ある時には強く激しく、ある時にはやさしく人の心に働きかけ、人の心に力と運動と安らぎを生ぜしめるエネルギーの呼称である」という定義は非常に難しいが、一方で美というのは表面的な外的な美と本質的な美があり、一時的な美と持続的な美がある。前者はわかりやすく一時的に商品価値が高いものを指し、後者は構造の美しさだと書かれており、これが自身ではしっくりくる言葉であり、先ほど述べた問いへのヒントのように感じたと語った。
 認定こども園こどものにわ西浦和幼稚園
認定こども園こどものにわ西浦和幼稚園
パネリストの発表の後は質疑応答が行われ、活発な議論が繰り広げられた。

−−催しの後、A-Forum代表の斎藤氏(写真右)にコメントをいただいた
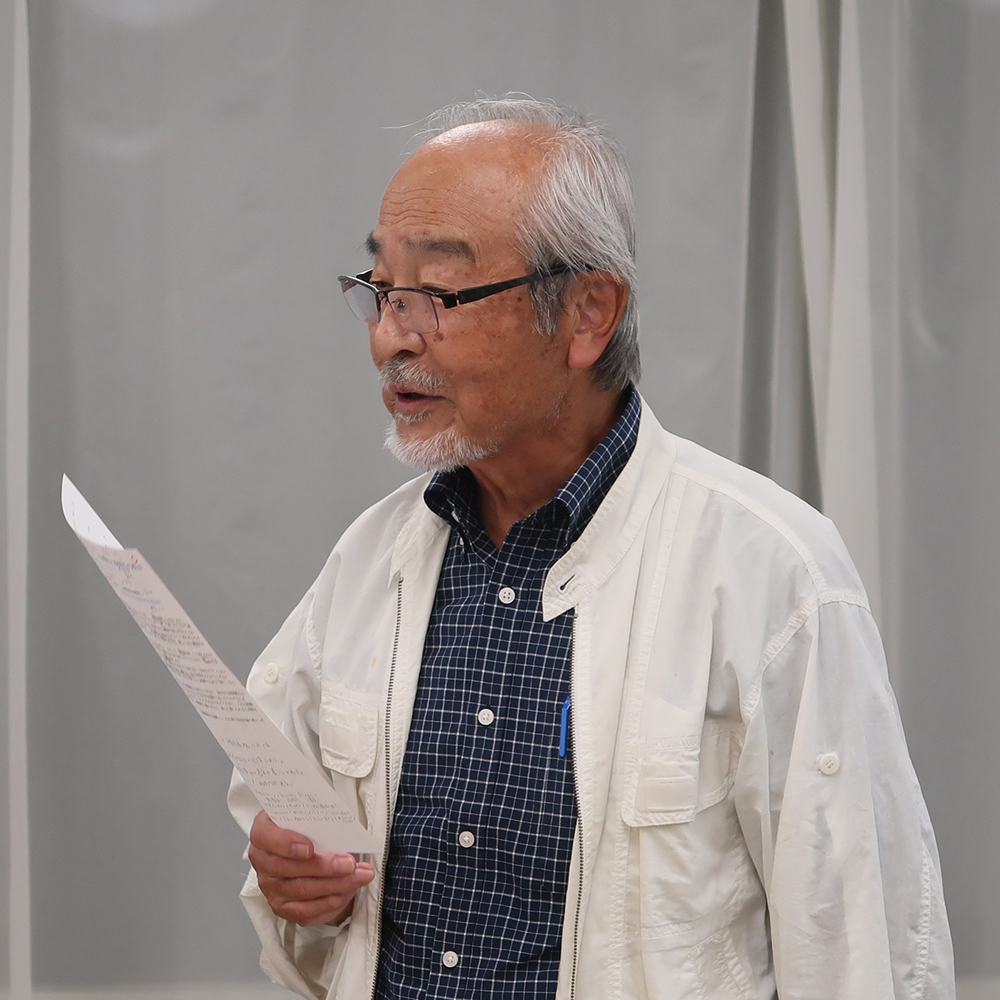 10年前に橋と建築の距離を縮めたいと考え、セミナーをA-Forumで行いました。その時にすごく面白かったので、またなにか展開できないかと1年前に建築ジャーナルで「美しい橋」という企画を八馬先生と渡邉竜一さん(ネイ&パートナーズジャパン)と作りました。建築と橋梁という別のフィールドの者同士の議論が噛み合った一つの土壌を作れたことはとても大きかったと思っています。また、八馬先生の著書である「橋をデザインする」(共著・技報堂出版 (2023/3/14))の中で推薦図書に私の「空間 構造 物語〜ストラクチュラル・デザインのゆくえ」( 彰国社 (2003/10/1))を挙げていただき、その解説には「著者は構造家だが学ぶべき橋の古典のほぼすべてが登場する。橋梁学徒必読の建築構造本である」と紹介してくださり、橋と建築が一体であるという私の考えがこの一文に凝縮されていてとても嬉しく思いました。さて、今回のテーマですが、構造美に関していうと橋は「元祖」であると考えます。私が一番好きな橋であるスイスのサルギナトーベル橋は、たった一つの集落に行くため深い谷を越える橋であり、風景の中にきれいになじんで宝石のように存在し、自然の景観の中に橋がどうデザインされるべきか問いかけている。これはまさに構造美だと思います。今回のフォーラムで非常に面白く感じたのは構造美とは「構造の美」なのか、または「構造と美」なのかというところを考えさせられました。パリのエッフェル塔は今ではなくてはならないシンボルですが、建築された当時はたくさんの意匠設計者たちが反対していました。芸術家には構造美はわからないのか? それは今の時代でも同じです。人によって違うし、時代によっても違う。構造美とは不変的なものだと思うのですが、そう思うと古典を学ぶということはとても大切だと思います。今後、AIなどの時代になってますますこのような議論が必要になってくると思います。
10年前に橋と建築の距離を縮めたいと考え、セミナーをA-Forumで行いました。その時にすごく面白かったので、またなにか展開できないかと1年前に建築ジャーナルで「美しい橋」という企画を八馬先生と渡邉竜一さん(ネイ&パートナーズジャパン)と作りました。建築と橋梁という別のフィールドの者同士の議論が噛み合った一つの土壌を作れたことはとても大きかったと思っています。また、八馬先生の著書である「橋をデザインする」(共著・技報堂出版 (2023/3/14))の中で推薦図書に私の「空間 構造 物語〜ストラクチュラル・デザインのゆくえ」( 彰国社 (2003/10/1))を挙げていただき、その解説には「著者は構造家だが学ぶべき橋の古典のほぼすべてが登場する。橋梁学徒必読の建築構造本である」と紹介してくださり、橋と建築が一体であるという私の考えがこの一文に凝縮されていてとても嬉しく思いました。さて、今回のテーマですが、構造美に関していうと橋は「元祖」であると考えます。私が一番好きな橋であるスイスのサルギナトーベル橋は、たった一つの集落に行くため深い谷を越える橋であり、風景の中にきれいになじんで宝石のように存在し、自然の景観の中に橋がどうデザインされるべきか問いかけている。これはまさに構造美だと思います。今回のフォーラムで非常に面白く感じたのは構造美とは「構造の美」なのか、または「構造と美」なのかというところを考えさせられました。パリのエッフェル塔は今ではなくてはならないシンボルですが、建築された当時はたくさんの意匠設計者たちが反対していました。芸術家には構造美はわからないのか? それは今の時代でも同じです。人によって違うし、時代によっても違う。構造美とは不変的なものだと思うのですが、そう思うと古典を学ぶということはとても大切だと思います。今後、AIなどの時代になってますますこのような議論が必要になってくると思います。当日の模様はA-ForumのYouTubeチャンネルでも視聴できる。https://youtu.be/6z05XfZWlAA






 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら