首都高メンテナンス東東京 2025年度安全大会を開催
首都高メンテナンス東東京(株)は、7月25日、東京・日本橋社会教育会館8階ホールで2025年度安全大会を開催した。会場には関係者190人が出席した。(井手迫瑞樹)
路面照射型矢印≪ムーブアロー≫や、ケーブル配線を省略した内照灯一体型デリネーターを今年から順次導入
今年度は会社設立以来、最大規模の事業量
路面照射型矢印≪ムーブアロー≫や、ケーブル配線を省略した内照灯一体型デリネーターを今年から順次導入
 開会挨拶で並川賢治社長(右写真)は、出席した協力会社に対し、「日々生じる緊急事象への対応、積雪凍結対策あるいは台風などによる気象災害への対応において、24時間切れ目のない体制の構築や現場での献身的な対応を担っていただいており、ここに改めまして、心より感謝を申し上げる」と謝意を示した。
開会挨拶で並川賢治社長(右写真)は、出席した協力会社に対し、「日々生じる緊急事象への対応、積雪凍結対策あるいは台風などによる気象災害への対応において、24時間切れ目のない体制の構築や現場での献身的な対応を担っていただいており、ここに改めまして、心より感謝を申し上げる」と謝意を示した。
さらに、「今年度の事業は、例年の土木維持補修に加えて、首都高速道路のETC専用化に向けた料金所入口での工事や、一定規模の関連事業の受注を見込んでいることから、会社設立以来、最大規模の事業量となっている」状況にあることを示した。また、「今年度に入ってから本日まで工事事故ゼロを継続している」ことに言及し、「本日の安全大会にて、改めて工事安全に関する認識を深め、安全活動を通じた 現場の更なる工事安全を目指したいと考えている」と述べた。
また、独自の施策にも言及した。例えば、危険な規制内進入事故を防ぐために、路面照射型矢印≪ムーブアロー≫や、ケーブル配線を省略した内照灯一体型デリネーターを今年から順次導入していく考えを示し、首都高の交通規制要領で推奨されているフルカラーLED予告看板と合わせて、いずれも夜間の高速上の交通規制において危険な規制内進入事故を防ぐことに貢献することを期待した。
加えて、現場の作業量を低減するため、カスタマイズした日報管理システムの昨年から導入についても語った。「従事者の事前登録情報やチェックリストを電子端末に容易に取り込むことができるため、日報の作成時間の短縮ができているのではないかと思う。今後は、システムの更なる改良に努めると共に、運用面の改善も進め、その結果生み出される時間を安全に振り向けていくようにしたい」と述べた。
波津久東京東局長 安全充填管理項目を示す
「コンプライアンス遵守の徹底」や「健康に働ける職場環境づくり」も掲げる
 来賓あいさつは首都高速道路(株)東京東局長の波津久毅彦氏(左写真)が壇上に立った。
来賓あいさつは首都高速道路(株)東京東局長の波津久毅彦氏(左写真)が壇上に立った。
波津久氏は「東局管内では首都高全体の交通量である1日約111万台のうち、約63万台を担っており、分担率は57%にもなる。管理延長は141.7kmであり、首都高全体の約4割に達する。約5割は開通から40年を超えており、施設の高齢化と担い手不足に伴い、日々のメンテナンスの高度化が求められている」と実情を語った。
その上で「この重要な社会インフラを守るにあっては、首都高メンテナンス東東京の皆様、そして協力会社の皆様の積極的な取り組みが不可欠である」と述べ、一層の奮起を促した。
また、東京東局の2025年度「安全管理重点項目」について
1) 火災事故再発防止対策の取組の徹底
2) 不注意による労働災害の防止
3) 構造物及び施設物の接触・損傷による公衆災害の防止
4) 工事車両による接触事故の防止と規制内進入事故の防止
を示し、法令遵守として「コンプライアンス遵守の徹底」(軽微な法令違反も許さない)、衛生管理として「健康に働ける職場環境づくり」(ハラスメントのない職場を目指す)も掲げた。
労働災害ゼロ・交通災害ゼロを掲げる
現場での基本動作・監視・声掛けを継続徹底
 次いで、伊藤寛執行役員兼安全・防災部長(右写真)が、同社の安全方針について述べた。
次いで、伊藤寛執行役員兼安全・防災部長(右写真)が、同社の安全方針について述べた。
2025年度における「安全衛生管理計画」を基に、工事安全管理の重点項目、過去10年の事故分析結果、具体的な再発防止策、そしてヒューマンエラー抑止のためのコミュニケーション文化づくりを確認・共有することを軸に、「特に、交通事故および規制内進入事故の増加傾向、重大化リスクの高い飛来落下・火災の再発防止、熱中症対策を強化すること」を強調した。
また、目標として、労働災害ゼロ・交通災害ゼロを掲げ、視認性資機材の導入・標準化、開口部の管理、監視・通報体制の強化を図ると共に、冒頭に並川社長が語ったように「視認性向上と規制強化の具体策として進入抑止・誘導の明確化、規制ラインの視覚訴求を強化、とりわけカラーコーンの高視認化(コーン下部に超高輝度反射シールを貼付し、規制範囲を遠方から可視化)、や内照灯一体型デリネーターの採用 (コーン上部に内照灯一体型(対称式)を装着し、ケーブル配線不要で単体発光を実現)を10月から順次導入し、利用者からの視認性向上を図っていくことを示した。さらに「視認性向上はリスク低減の一要素に過ぎない」とし、現場での基本動作・監視・声掛けを継続徹底することで、ヒューマンエラー対策とコミュニケーションの深化を図り、「うっかり」「危険と思わなかった」「大丈夫だと思った」などの過信・思い込みが重なって発生する事故を未然に防止していこう」と話した。


.jpg)



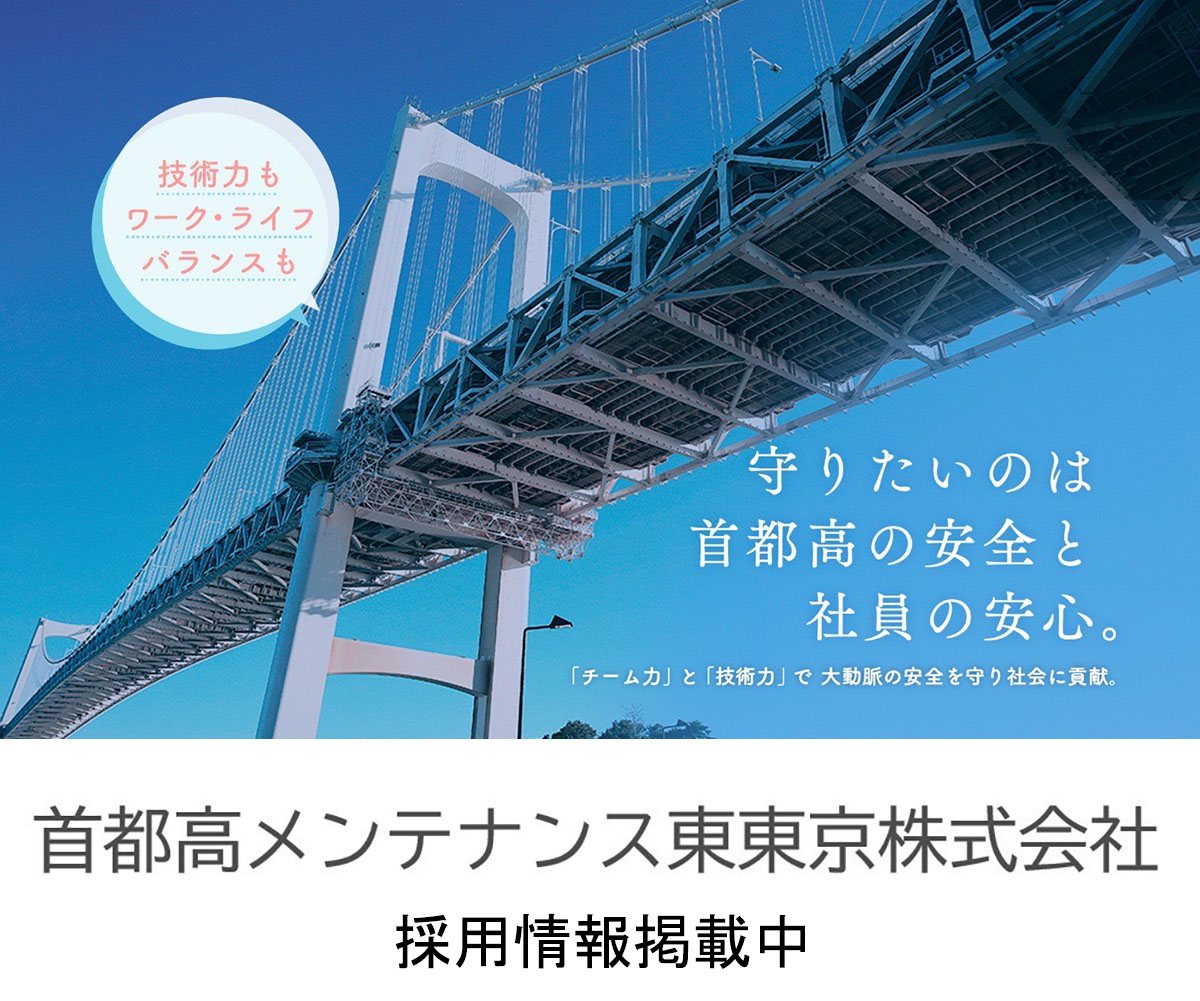




 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら