新しい時代のインフラ・マネジメント考
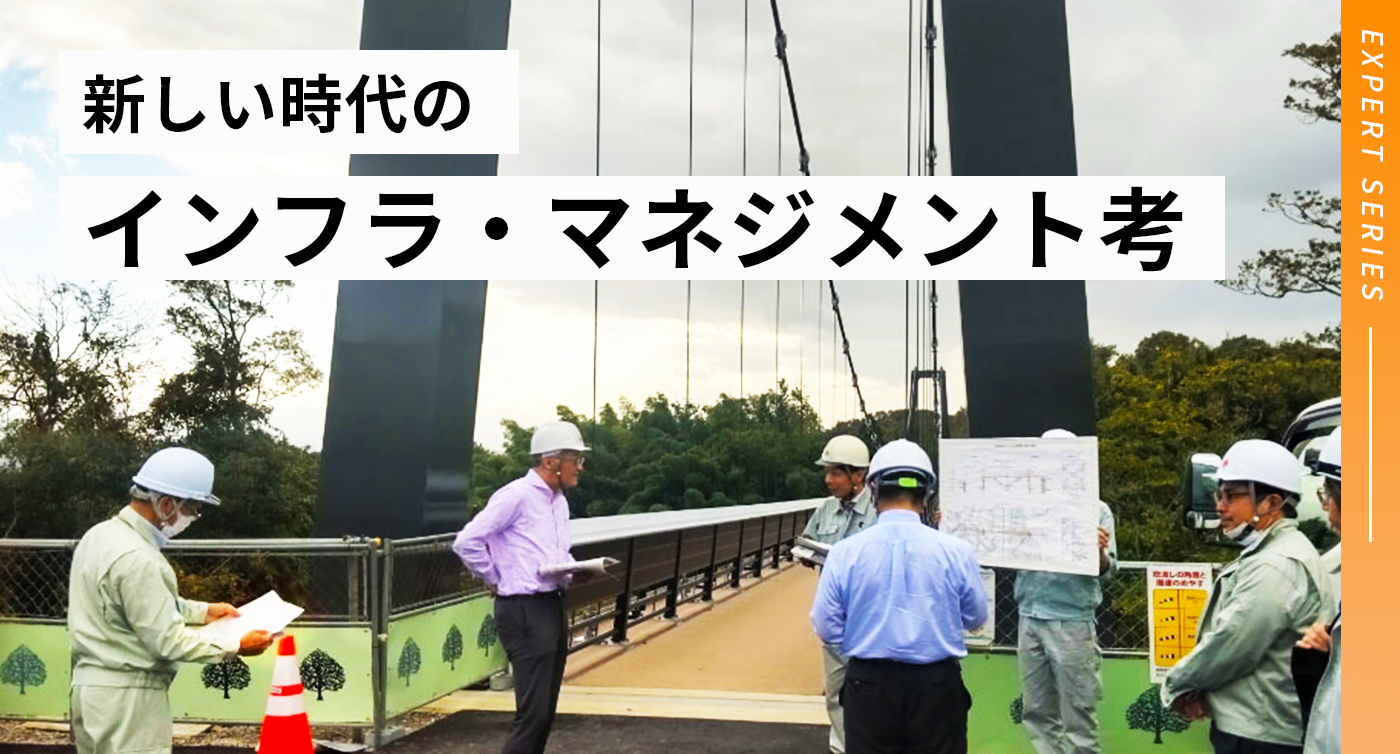
⑭続 新技術がなぜ導入されないか?

植野インフラマネジメントオフィス 代表
一般社団法人 国際建造物保全技術協会 理事長
植野 芳彦氏
1.はじめに
前回、新技術の導入に関する私の考えを書いた。これまで、あまり関連のない方々からの問い合わせがあるが、継続的ではない。これは、あきらめたのか? すべてがわかったのか?(つもり)また別の方に相談しているのか?・・・・私は本音しか言わないから、いい加減で冷たくとられるのかもしれない。しつこいくらいのお互いの努力が必要なんですがね。
人それぞれ、考え方は違う。これは当然のこと。しかし、それが、的外れか、効果がないかの判断をしていかなければ、徒労に終わる。これができるようになるには経験による勘しかない。
2.「新技術の導入」つづき
前回、導入するための手法について書いたが、最近やっと気づいたことがある。気づいたというか、自分なりに納得した。簡単に言うと結局みなさん、勉強していないんですね。うわべで分かったつもりでいる。まず、安易に特許を取ればよいと、考えている方が多い。我々がやろうとしているのは、公共事業だということが問題だ。発注時には透明性、公平性が求められる。独禁法が問題になる場合があるので、気を付けなければならない。コストの問題もある。いわゆる特許料である。
本来公共事業であれば、技術審査証明を取ればよいのだが、これを取得するには労力と時間、費用が掛かる。NETISに比べると相当な違いがあるので皆、躊躇するが、NETISはその中身を保証するものではないことが、みなさんわかっていない。
発注の仕組みに関しても勉強しないと、導入は遠い。偶然相手が、わかったふりして採用される場合はある。しかし、危うい。発注側は、コンサルが提案してきた工法などを安易に採用している場合が多いが、危うい話である。よく、無駄な補修をしているという話もよく聞く。これも、評価がきちんとできていないからであり、本来は、3巡目になってきたので、かつて実施した補修の評価も実施すべきである。これを報告していけば、長期的に見れば有効である。国、県、自治体とそれぞれ少しずつ違っているが、その辺の、実態が理解できずに、安易に判断している。特に技術一辺倒の人たちは危うい。


これを「断面欠損だ」と、コンサルはいう。施工時の問題である。何がしたかったのか?
どうも世の中を見ていると、「思いつき」や「キーワード」を聞いてわかったつもりになっている方々が多いのが、気になる。それだけ賢いのかもしれないが、残念ながら受験勉強とは異なり、そんな簡単に理解できるはずはない。それまでの、実務での経験による勘や、相手方の状況も勘案して判断しなければならないのである。
3.とにかく勉強しなければ
官側は、本当に何が必要なのか? の判断ができなければ無駄なことをやっていく。業者の言われるがままに採用していけば、何の効果も出ない。課題の、本質を考え、どういう方法があるか?それは有効なのか? 判断できる技術力と、情報源を持つことが重要である。
民側は、発注の仕組みや法律、特に独禁法などを学ぶ必要がある。しかし、発注の仕組みは、難しい。なかなか経験豊富な方でも理解していない場合がある。「自分の会社も、入札に参加したい。」という企業がある。しかし、ここで、「業者登録はしているのか?」と聞くと、していなかったりする。これでは参加資格はない。「まずは業者登録からしてください。」という話になる。これで初めて土俵に上がれる。
次に、実績の構築と営業である。営業は、来なければ、覚えられないし、そもそもが指名されない。指名されるのには、ある程度の実力が要求される。しかし、最近は役所の方が、カウンターでシャトアウトしているので、なかなか職員に説明ができない。これはお互いに、情報に関する損出である。情報漏洩や談合などが疑われるからであるが、お互いの勉強が足りなくなる。
本来であれば、官側が積極的に勉強し、学会や展示会、セミナーなどへの参加、技術雑誌の購読など情報収集を普段からしなければならないのだが、そういうことを積極的にできる職員は残念ながら希少である。
民側も同様で、官側のニーズや、動きを各種公的な講演会やセミナー、論文などで収集しておく必要があるが、これもどうも希薄である。
なので、新技術などの導入に関して、様々なことが言われるが、結局はシーズとニーズが合わなければ採用はされない。
無理にこれをやろうとすると、法律的におかしなことになり疑われるので注意する必要がある。
技術的には、その効果と耐久性が特に重要となる。効果がなければお互いの不利益になり税金を使っているので税金の無駄遣いとなる。私が一番疑問に思っているのが、ひび割注入である。果たしてその効果は?どうなのか。もう始められて10年たつのでその効果や再劣化の具合を検証し本当に有効なのか確認する必要がある。なぜ問題か?とにかく工費が高い。水の侵入を防ぐという効果は、再劣化さえなければある程度までは、効果があるだろうが、水を止めると言うことは非常に難しい。
コンクリートのひび割れの原因は様々な原因があるが、結構鉄筋量の不足がある。本来ないはず、なのだがあるという事実も気にすべきだろう。設計ミスや施工不具合である。全部が全部、完ぺきに設計され完璧に施工はされていない。まあ、ここは多くは書かない。

ひび割れ補修の跡が良くわかるが、ひび割れは、再び開いている
これが、ひび割れ注入の現実。これが「予防保全」となるのか?






.jpg)






 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら