インフラ未来へのブレイクスルー -目指すは、インフラエンジニアのオンリーワン-

⑦なぜ、日本の橋は落ちないのか? -災害は忘れたころにやってくる‐

(一般社団法人)日本構造物診断技術協会 顧問
アイセイ株式会社 技術開発担当部長
髙木 千太郎氏
1.はじめに
令和7年度も残り3カ月となり、巳年(みどし・へびどし)のラストスパートの時期となった。今年の中期を振り返ると、梅雨らしくない少雨の初夏から秋のお彼岸までまるまる4か月、茹だる様な酷暑が続き心身ともに疲れ果てる日々もようやっと一息つき、心地よい秋が来たと思ったら、またもや夏日の復活である。読者の多くも感じているように、今年の暑さは本当にしぶとい! 一昔前の我が国における四季の季節感であれば、この時期、すぐそこに冬の足音が聞こえてきて、冬支度真っ最中のはずである。ここ数年は、夏が来るたびに地球温暖化と温暖化抑止が繰り返し叫ばれてはいるが、要となる人間は口先だけの警告に終始し、次世代のことなど全く考えない行動が続く。中でも特に残念なのは、大量の熱を発して多くの人を死に追いやる侵略戦争を好んで進め、全く辞めようと努力もしない。地球に暮らす人間は、神も恐れぬあきれ果てた知恵を持つ獣である。地球上で最悪の獣、人間の話は尽きないのでここらで終わりとして、本題に移るとしよう。
我が国のインフラに目を向けて考えると、これだけ暑い日が続くと、構造物は限界値まで伸び、アスファルト舗装は設定針入度をはるかに超えて柔らかさが増し、轍が増すなど考えただけでも恐ろしい。夏日が続く極暑の中私は、これまでの経験では図ることの出来ない事態が起こるのではと、不安な日々を送る毎日である。
当初設定した設計条件が異なることから当然、構造物、特に橋にとって、設計では想定していない環境下での使われ方をし、人と同じように何らかの異常が発生しているはずである。しかし、今回の連載における主人公である橋は、このところ酷暑が続いても異常事態も発生せずに、静かに耐え忍んでいる。この感覚が理解できる人は、夏季の炎天下において、鋼製橋梁の製作における仮組、製品検査及び地組の段階で鋼床版箱桁の中に入ったことがある人は実感しているはずである。
連日の猛暑に疲れ果てている私は、今回の主題として、「なぜ、日本の橋は落ちないのか? Why don’t Japanese bridges collapse?」を選択した。
我が国の橋がなぜ、落ちないのかを話題提供しようと考えたのは他にも理由がある。実は橋梁界の重鎮であるM名誉教授との久々の会話の中で、落ちない橋が話題となったからである。M名誉教授は、常日頃から我が国の橋梁メンテナンスに関する思い入れがあり、自らが主体で進めてきた「SIP事業」や「プリズム事業」に対する反省的な発言が多い。私にとってM名誉教授の話は常に新鮮であり、特に米国の話しは面白い。M名誉教授は、我が国の橋梁関連技術をリードしてきた第一人者であり、それなりの責務を負う立場であるが、心を許して語るM名誉教授が海外で得た種々の経験談は、多くのヒントが隠されており、聞いている私のエネルギー源ともなっている。
今回、久しぶりにお会いしたM名誉教授曰く「髙木さん、我が国の道路橋メンテナンスを押し進めてきたのは私ですが、今行われている定期点検の質の低下は眼を覆うばかりですね」と手厳しい。確かに、今回の定期点検要領や提出書類の改訂内容を見るに、疲労やアルカリ骨材反応などの代表的損傷を明記し、専門家のコメントを重視する姿勢は分かるが、私が重視している担当技術者に不可欠な想像力を伸ばすことが出来るのであろうか?M名誉教授の話は続く、「髙木さん、それにしても日本の橋は落ちない。出来が良いのかな?」、一息ついて、「わが国で、橋梁の1つでも落ちると真剣な議論になるが、なぜだろうね、橋が落ちないのは」と何時もの話に終着した。
私がこれまでに学んできた橋の現代社会おける立ち位置は、人々の生活と経済活動を支えるために不可欠な社会基盤施設となっている。道路や鉄道のネットワークを構成する要として、毎日数百万人の通勤・物流を支え、災害時には地域の生命線としても機能している。そのため、一度崩落事故が起これば、甚大な人的・経済的損失を招くことは、世界の事例が繰り返し示してきた。
海外では、設計や施工の不備、維持管理の不足、自然災害の影響などにより、重大な橋梁崩落事故が各国で発生してきている。私も連載で何度も取り上げている図‐1に示すミネソタ州のI-35Wミシシッピ川橋梁(2007年)、図‐2に示すイタリア・ジェノバのモランディ橋(2018年)、そして図‐3に示すブラジル・Juscelino Kubitschek de Oliveira Bridge(オリベイラ橋)の崩落事故などは、その典型的事例である。これらの事故は「橋は恒久的な構造物ではなく、管理を誤れば脆くも崩れ去る」という現実を我々に突きつけている。一方、日本では高度経済成長期以降、膨大な数の道路橋・鉄道橋が整備されてきたにもかかわらず、大地震発災や洪水による流失以外、大規模な崩落事故は皆無である。

図‐1 ミネアポリスI-35W高速道路橋・米国

図‐2 モランディ橋・イタリア

図‐3 ジュセリーノ・クビチェック・デ・オリヴェイラ橋:ブラジル
私が考えるにこの背景として我が国には、設計基準の厳格さ、施工技術の高度さ、そして定期点検制度をはじめとする維持管理体制の確立があげられる。特に我が国においては、兵庫県南部地震(1995年)以降耐震補強が全国規模で進められ、その結果、東北地方太平洋沖地震(2011年)においても多くの橋が致命的な被害を免れたことは記憶に新しい。
しかし、本当に「日本の橋は崩落しない」と断言できるだろうか。確かに他国に比べて落橋リスクは低いが、高齢化(老朽化)、気候変動、豪雨による洗掘や地震といったリスクは常に存在する。社会資本の大半が高度成長期に建設されてから50年以上を迎える現在、我が国の行政技術者及び関連技術者は、リスク排除のために今以上に予防保全の姿勢を持ち続けなければならない。
今回の話題提供では、日本の橋がなぜ崩落事故をほとんど起こさずに今日まで維持されてきたのか、その背景を設計・施工・維持管理・制度面から整理し、あわせて将来に向けた課題と展望を考察する。我々技術者は、安全神話に安住するのではなく、実証と改善を積み重ねる姿勢こそが、今後の社会インフラの安全・安心を国民に提供する考えの根幹を成すのである。
2.なぜ、日本の橋は落ちないのか?
橋は、人と物の移動を支える社会基盤の中核である。橋の安全性は人命と経済活動を直接的に左右する。世界各地では、橋の崩落事故が繰り返し発生し、多数の死傷者や交通網の寸断を引き起こしてきた。しかし日本では、約72万橋(国土交通省資料より)に及ぶ道路橋や約8万8千橋(鉄道事業者管理データより)の鉄道橋が存在するにもかかわらず、海外に見られるようなメンテナンス不足が関連する大規模な崩落事故はほとんど発生していない。私の記憶では、島田橋(岐阜県・1963年)と新菅橋(長野県・1965年)の2橋のみである。本章では、我が国の橋がなぜ「落ちない」のか、その要因を多角的に考察する。
2.1設計基準の厳格さと信頼性
まず始めは、我が国における道路橋の設計基準について考えてみる。
日本の橋梁設計は、「橋、高架の道路等の技術基準」を具体化した図‐4に示す「道路橋示方書・同解説」に代表されるように、世界でも屈指の厳格さを誇る。特徴の第一に安全率の設定がある。道路橋においては、荷重、材料強度、地震作用などに対してバラツキを吸収し、十分な余裕度を持つように安全率を設定し、今日に至っている。また、地震多発国日本として、耐震設計の基本的な考え方を大きく変える事象、図‐5に示す兵庫県南部地震による被災を契機に、橋脚や支承に対する耐震補強が全国的に進められ、最新の設計基準では動的解析に基づく高精度な耐震性能評価が義務化されている。さらに、近年著しい異常気象への対応策として、豪雨、積雪、塩害など多様な自然条件に応じた設計指針が整備されてきている。


図‐4 道路橋示方書・同解説 1共通編 / 図‐5 兵庫県南部地震における被災状況
先に示すような事象が明らかとなるその都度、設計基準は改訂され、国際基準に劣らぬ水準で安全性を担保している。
2.2. 高度な施工技術と品質管理
先に示すような設計が如何に優れていても、施工が不十分であれば崩落事故発生等は避けがたい。我が国の橋が信頼される理由の一つは、施工段階における徹底した品質管理がある。落橋に至らない第一の要因として、我が国が誇る熟練した施工管理や竣工検査の徹底があげられる。例えば、コンクリートの打設管理や鋼材の溶接技術(図‐6参照)など、細部にわたる精緻な施工が伝統的に培われてきたことと、施工中の第三者検査、非破壊検査、現場試験が制度的に古来から現代まで確立されている。また、橋梁の製作・施工時に行われた個々の種々な施工管理データの蓄積があげられる。例えば、橋梁に使われる材料の製造履歴、仮組み立てや地組立て等の施工記録がファイリングシステム等で確実に保存され、供用開始後の維持管理にも役立てられている。このように、日本の橋梁は「造る時点から壊れにくい」構造物として築かれているのが特徴でもある。

図‐6 溶接技術と資格証明
2.3 維持管理制度と点検文化
橋が「落ちない」最大の理由は、我が国において供用開始後に継続的に行われている維持管理制度にある。好意的に解釈すると、定期点検の義務化があげられ、道路法改正により5年に一度の近接目視点検が義務化され、本年度から3巡目の定期点検が行われている。さらに、先の定期点検を行ってきた点検結果は「健全度」により分類され、国が整備した「xROAD」データベースシステム等をベースに予防保全的な補修や補強が全国的に実施されている。併せて、診断技術の高度化も特徴としてあげられ、赤外線、ドローンやAI画像解析などの先端技術が、国をはじめとして各高速道路会社に導入され、これまで見逃されやすかった損傷も早期に検出できるようになってきている。
こうした我が国が進める点検文化は、橋を「建てっぱなし」ではなく「育て続ける」資産とみなす姿勢の表れと言える。
2.4 制度と社会的要請
日本社会は、高度経済成長期が終焉を迎え、一時期に多くの橋梁を建設していた時代から、道路橋や鉄道橋の高齢化が課題となって以降、安全性に対して高い水準を求めてきた。また、笹子トンネルの天井板落下事故以降、図‐7に示す道路メンテナンス会議の設置など、中央官庁と地方自治体の連携として、国土交通省によるガイドラインと地方自治体の実務が一体となり、全国レベルで統一的な管理体制が整えられている。これも私の日頃の発言とは異なる好意的な解釈と言われそうであるが、土木学会や研究機関によって得られた種々な知識が設計・施工・維持管理に反映され、最新知見が迅速に制度に取り込まれている。さらに、我が国においては、「重大事故はあってはならない」という社会的合意が強く、行政・技術者に対して不断の安全確保を迫っている。これまで上げた種々な取り組みや姿勢による「安全に対する社会的圧力」が、諸外国の多くに見られない水準の安全文化を生み出している。

図‐7 道路メンテナンス会議規約と開催状況
日本の橋が世界的に見ても崩落事故をほとんど起こさないのは、設計・施工・維持管理・制度・社会文化が有機的に結びついているからである。すなわち、単なる技術力だけでなく、「橋を守り続ける」という社会全体の姿勢が安全性を支えているとも考えられる。本章の結論は明快である。日本の橋は偶然に落ちないのではなく、膨大な努力と制度の積み重ねによって「落ちにくい」仕組みが築かれていることがあげられる。
我が国の橋が大規模な崩落事故をほとんど経験せずに今日まで維持されてきた背景には、設計・施工・維持管理、さらには社会制度や文化といった多層的な要因が存在する。しかし、その根幹にあるのは、やはり設計段階における基準の厳格さである。
橋梁は完成した瞬間から劣化が始まるが、その寿命を左右する第一歩は「どのように設計されたか」で決まる。日本の設計基準は、単に強度や安定性を担保するための数値規定にとどまらず、自然災害の多い国土条件を背景に、耐震性や耐久性を徹底的に織り込んでいる。さらに、基準は時代ごとの知見や事故からの教訓を反映し、常に改訂を重ねてきた。
したがって、日本の橋が「落ちない」という事実を理解するためには、その基盤となる設計基準の体系を紐解くことが不可欠である。次章では、我が国の橋梁設計基準の歴史的変遷と構成原理を整理し、安全性を支えてきた規範の仕組みを詳しく見ていくこととする。







.jpg)

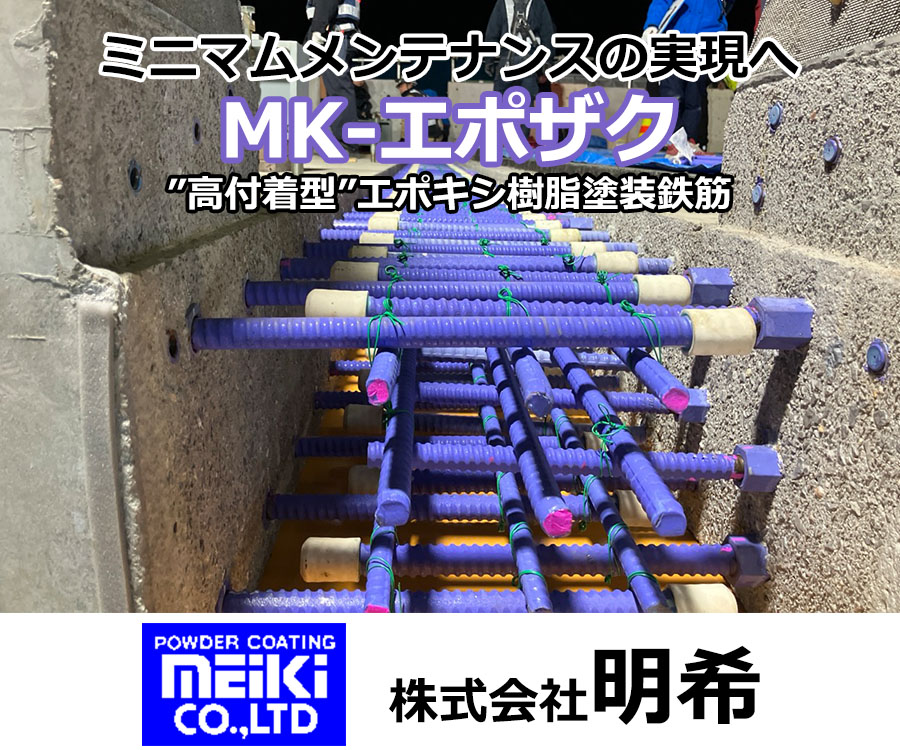
.jpg)


 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら