新しい時代のインフラ・マネジメント考
4.まとめ
「新技術」と「マネジメント」が今後の軸である。これらをしっかりやっていかないと、荒廃する町にしてしまう。デザインは、余裕があればその次である。今の危機的状態をどうだ出するかが重要である。民間企業もそこを理解して、生き残りを考えればよい。細かな話をしても始まらない。どうも、難しく難しく考える人たちがいる。そういうのが好きな方々もいるだろうが、それは時と場合によれば、である。押し売り営業にごまかされてはいけない。食い物にされてしまい責任は取ってくれない。よくよく相手を判断することである。
とにかく発注者が、しっかりとした意志を持ち考え長期ビジョンを持つことである。
新技術の導入も、マネジメントに関しても、国やNEXCO、JR、旧公団と自治体では状況が大きく異なる。自治体でも各々の状況は異なっていることが、やっと議論されるようになった。各自治体の状況や都合は異なるので、考えることが重要である自治体が主役にならなければ、ならない。橋梁の92%は自治体で管理しているのである。また、国と自治体は、同一の示方書を使用しているが、NEXCOなどは設計思想が若干違う。これは当たり前のことなのである。さらにJRは違う。さらにさらに、農林系では設計しているコンサルが建設コンサルではなく農林のコンサルである場合が多く、広域農道などは市町村に移管されているが、管理者が苦労する場面がある。事情がそれぞれ違うのである。何が言いたいかというと、出来が違うので管理者の状況は異なってくる。
先日、国土交通大学校の「塩害ASRコース」の方々が、実習の一環として富山の橋梁を視察された。私も立ち会えと言うので立ち会ったが、おいでになった方々は、例年になく幹部の方々だった気がする。雨天の中、大変ご苦労様でした。その折に、先導の講師である、T先生(NEXCO中日本の顧問でもあ)るとお話しさせていただいたが、昨年撤去したオーバーブリッジに関し、「あれは撤去して正解だった。」と言われた。私は10年前に一見して危険性を指摘し、撤去を決めモニタリングなどによる監視を指示していたが昨年やっと撤去できた。最大の問題は撤去費用であった。工法も問題があった。しかし先生曰く撤去後に、撤去ブロックを見たが、クラックが想定外の場所にも発生しており、やばかった、危なかったと、間に合ってよかったとのご意見であった。私もそう思う。こういったものも、全国にまだ数多く存在している。それが自治体の都合と重なり危険因子を放置していることもある。全部が全部そうではないが、危険なものは早期の撤去は重要である。また、それを見抜く目が重要である。うわべのひび割れだけを拾って安心していると想定外の崩落がいつ起きるかわからない。みなさん安易に考えているが、構造系が崩れれば崩落は簡単に起きる。これは理想論では止められない。
1人では何もできない。実現できない。多くの協力者が必要である。技術的にも、1件1件実施する時代は終わり多数を一度に対応しなければならない時代になった。往々にして技術者はここを忘れていると言うか、理解したくないのであろう。多数の物を管理していかねばならない技術は、標準化がその入り口となる。そしてマネジメント力である。これが欠けている。自分の考えを持つのは結構で必要なことであるが安易に他人の意見を受け入れてしまうのも問題である。


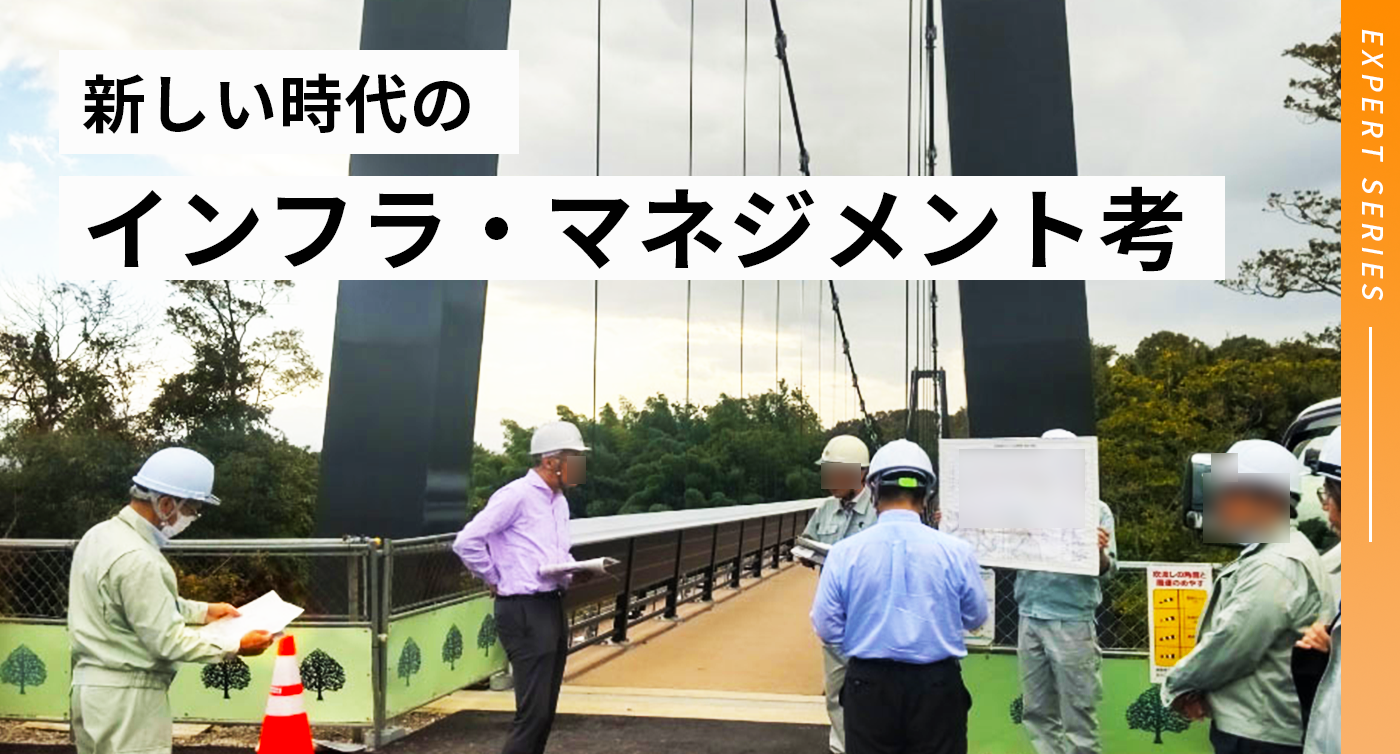






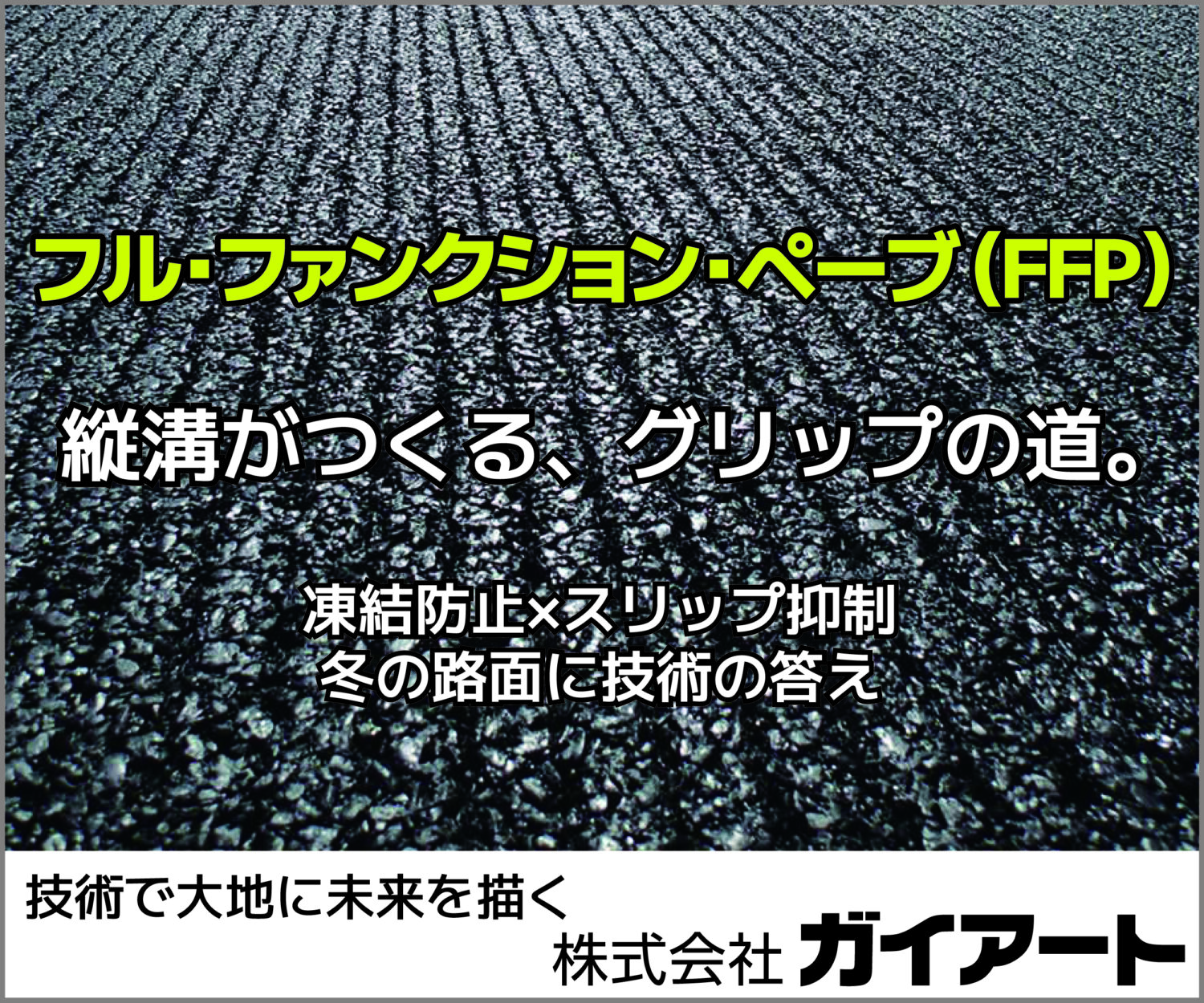




 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら