まちづくり効果を高める橋梁デザイン
はじめに
早いもので今年ももう11月です、東京はだいぶ寒くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。今回もご覧いただきありがとうございます。前回の「維持管理と景観の両立を目指す」と題した原稿では励ましのお言葉をいただきました。とても感謝しております。第2弾を出せるように準備したいと思います。
さて今回は9月にオランダ・ドイツのまちづくり調査をおこなう道すがら、いくつか興味深い橋を見てきましたのでご紹介したいと思います。
1.シーアシュタイン・ライン橋(Rheinbrücke Schierstein)
最初に紹介するのは、2025年度のドイツ橋梁建設賞1)の道路・鉄道橋部門の優秀賞を受賞したシーアシュタイン・ライン橋です。ドイツのマインツ(ラインラント=プファルツ州)とヴィースバーデン(ヘッセン州)を結ぶアウトバーン(A643高速道路)がライン川を渡る区間に架けられた橋です。
ここには、1960年代前半に架けられた既設の橋がありました。ただ建設当初の2万台/日に対し、現在は12万台/日を超える交通量となったこともあり、1990年代後半に疲労による損傷が発生し、2006年に架け替えを決定しました。
2007年に設計コンペが実施され、土木エンジニアリング会社のグロントマイ社(Grontmij GmbH)と、フランクフルトに事務所を構えるハイデ建築事務所(HEIDE – Ferdinand Heide Architekten)のJVチームの案が選定されました。ちなみに、グロントマイ社は、その後、ヨーロッパのスウェコ(SWECO)に合併吸収されています。
新しい橋の構造形式は、12径間連続の鋼箱桁橋とPC単純桁橋で、全長1280m、総幅員21.1m、最大支間205mです。ライン川の中洲にまたがっており、陸上部ではPC床版、渡河部では鋼床版となっています。また橋から吊り下げた歩道がついているのも特徴です。
施工は、まず下流側に新設の橋梁を建設し、その後、上流の既設橋を撤去した後に、もう一つの橋を施工しています。下流側の橋が2017年竣工、上流側が2023年に竣工しています。

写真1:ライン川下流左岸からの眺め
維持管理と景観を両立する橋(陸上区間)
前回、維持管理と景観の両立を取り上げましたが、この橋もそれを達成している橋です。
写真2は陸上部区間で、2箱桁になっています。桁は溶接ですのでボルトはありませんし、吊金具もついていません。合成構造になっているため、横桁は支点上にしか設けられていません。その横桁も厚板に穴を開けたシンプルな構成で、非常にスッキリしています。
V字の橋脚の中央部分が切りかかれていますが、これは支承を検査するためのスペースです。支承部分には、鳥よけのためなのか、メッシュのカバーがかけられていますが、橋脚の形状をそのまま延長する形にすることで違和感なく収められています。
写真3は、橋台付近の支間を撮影したものです。橋台に向かって2箱から1箱になるのですが、その変化も曲線でつないでいてきれいに仕上がっています。黒く見えるのは、桁内への進入路です(写真4)。

写真2:陸上区間の眺め

写真3:橋台付近の支間、右側に橋台がある

写真4:1箱から2箱への擦り付け部
写真5は、添架されている歩道橋です。床版とウェブから吊り下げる形となっています。写真2を見ていただくとわかるように、橋脚とつなぐことで橋軸直角方向の揺れを止めています。ちなみに私も関わった太田川大橋では千鳥に吊っています(写真6)千鳥の方がスッキリしているかなと思います。

写真5:陸上区間を側面から見た様子

写真6:太田川大橋








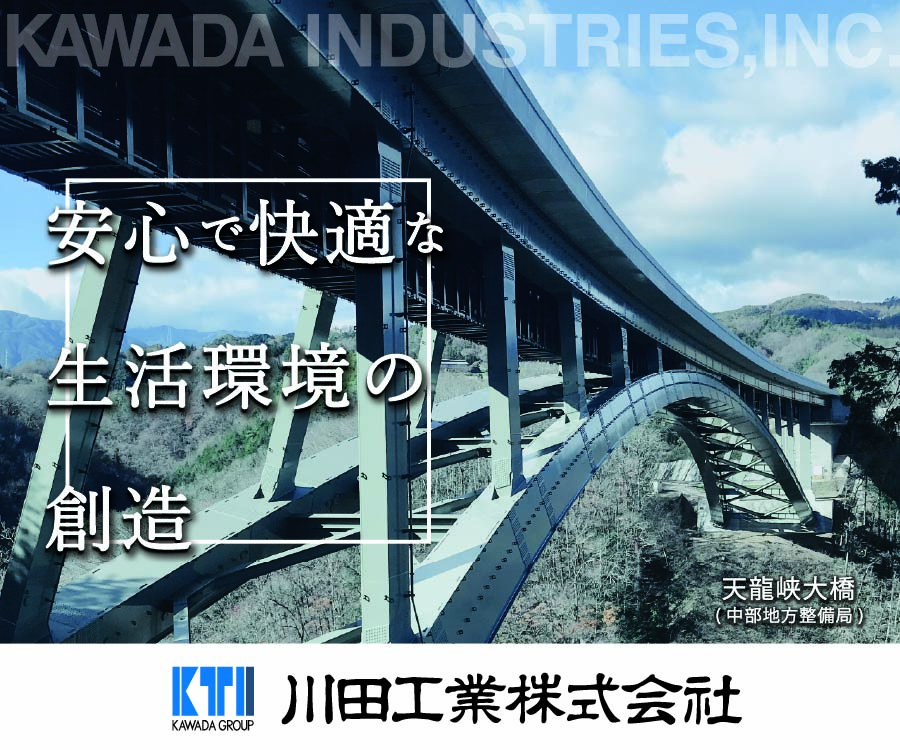






 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら