能登復興特集① 奥能登の復旧・復興状況
概要動画Overview Video
石川県奥能登地方は昨年、2度の大規模災害に見舞われた。記者は奥能登、とりわけ輪島に中学の修学旅行で行って以来、親しみを持っている。御陣乗太鼓も体験したし、投網体験もした。輪島塗など、伝統工芸も盛んで、外浦の景色は大変美しい地域である。珠洲市は人気漫画(アニメ化もされた)『スキップとローファー』(髙松美咲著、講談社)で主人公のふるさととして一躍脚光を浴び、さらに発展しようとした矢先に、大変な災害に見舞われた。記者は2000年代中盤から災害現場を取材しているが、東日本大震災や九州北部豪雨、熊本地震、球磨川の水害など取材を重ねるにつれ、地震と豪雨が重なって地域を襲う可能性は今後否定できないと発信してきた。その実例が残念ながら奥能登で生じてしまった。奥能登の被災、復旧・復興は他人事ではない。これからの日本の縮図でもある。地震発災直後~豪雨~現状とこれからについて石川県奥能登土木総合事務所の寺田龍彦所長にインタビューした内容をお届けする。(井手迫瑞樹)
市道まがき線のおさよトンネル約1.4kmを輪島市から権限代行で調査進める
地震や水害によって損傷した道路、河川、砂防、海岸は国げ権限代行
市道まがき線のおさよトンネル約1.4kmを輪島市から権限代行で調査進める
――事務所の職掌範囲(県管理道路や、基礎自治体から権限代行を受けて復旧復興を進めている道路や河川など各所土木インフラ)を概略的かつ延長や規模などについては定量的にお答えください
寺田所長 奥能登土木総合事務所は、輪島市、珠洲市、能登町、穴水町など奥能登地方の2市2町内の道路、河川、地方港湾および漁港、砂防、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、海岸等の整備、管理を担当しています。
国道および県道は44路線642km、そのうち構造物は556橋、27箇所のトンネルを管理しています。
河川は47河川238km、港湾は地方港湾を5港、漁港を5港管理しています。
三方を海に囲まれていることから海岸線は長く、特に海岸保全区域は19区域94kmもの延長を管理しており、その長さは県管理全体の半分に達します。
砂防指定地は、234箇所1,197ha、地すべり防止指定地は88箇所2,813ha、急傾斜地崩壊危険区域は236箇所530haで土砂災害の危険性が非常に高い、厳しい地域といえます。
当事務所が管理する砂防、道路、海岸のうち、国道249号の外浦に面している道路やその構造物、宝立正院海岸、町野川水系の砂防事業、河原田川水系河川事業などの災害復旧事業については、国の権限代行事業として委託しております。
逆に輪島市が所管する市道まがき線のおさよトンネル約1.4kmについては、輪島市からの権限代行事業として当事務所が災害復旧事業を行っています。同トンネルは、地震により覆工コンクリートの崩落や、クラックが確認されました。現在は、覆工コンクリートを部分的に取り壊して、支保工などや地山状況の調査を進めています。
-rotated.jpg)
おさよトンネルの損傷状況
.jpg)
同トンネルの応急対策状況
.jpg)
.jpg)
地震によって損壊した河川(左は八ヶ川の輪島市門前町山辺付近、右は鳳至川の輪島市二俣町付近)
地震 県内道路被災箇所の半数以上が奥能登に集中
19河川で河道閉塞、28河川で護岸崩壊。海岸は全域に渡って護岸が損傷、外浦では大規模な海岸の隆起
――2024年正月の地震における被災状況は
寺田 昨年正月の地震によって大規模な落石や斜面崩壊などが見られたほか、トンネルや橋梁も各地で被災しました。県内では県が管理する道路のうち42路線87箇所が被災して通行止めとなりましたが、その実に半数を超える箇所が奥能登に集中しました。奥能登へのアクセスルートは遮断された状態に陥りました。
河川は19河川で河道閉塞が生じ、28河川で護岸の損壊が生じました。さらに軽度な損傷は数知れず生じました。
海岸は全域にわたって護岸が損傷し、外浦では海岸線の大規模な隆起が生じました。年々、侵食により海岸線は後退していましたが、今回場所によってはこれが前進する事象が生じました。
港湾・漁港については、とりわけ輪島港が、海底隆起により大きな被害を受け、停泊していた多数の漁船が動けなくなりました。そのため、泊地の浚渫を行い、船を動かせるようにしました。また、既存の物揚場を切り下げて船への乗り降りができるようにしたり、仮設の浮き桟橋を設けて水揚げを可能にしたりするなど、漁港の機能を回復しました。今後も港内の浚渫を行い、水深を確保していきます。


海岸の隆起、拡大した砂浜(井手迫瑞樹撮影)
鹿磯漁港については、泊地が岩礁であるため簡単に浚渫ができず、エリアの中で地元漁業者と意見を交えて対策を考えていきます。


隆起した漁港(左は鹿磯漁港、右は輪島港)
車の通行における困難な状況は国土交通省や自衛隊等との連携によって徐々に開放されていきました。落石、崩土や橋梁の段差などの解消を行い、まずは2市2町の市役所、役場までの連携ルートの確保、孤立集落の解消に向けて応急復旧を進めました。その結果、豪雨前には13路線31箇所まで通行止めは解消されていました。孤立集落は完全になくなり、その後、新たな災害が起きないように道路の拡幅や応急的な崩落対策を進めていました。橋梁においては落橋こそありませんでしたが、珠洲市の藤見橋(橋長45m、鋼単純トラス橋)では大きな変位が生じていることから、同橋においては架替えを行う予定としており、現在は撤去工と仮橋工事を発注しており、架替え橋は設計を進めています。
IMG_2698.jpg)
.jpg)
橋梁の段差発生状況① (左は国道249号白潟橋(穴水町中居)、右は同川嶋大橋(穴水町川島))
RIMG3563.jpg)
IMG_2564.jpg)
橋梁の段差発生状況②(左は大谷狼煙飯田線粟津川橋、右は七尾輪島線井蓋橋(輪島市小泉付近))
.jpg)
粟津川橋の応急対策状況
県が管理するトンネルは、国に権限代行したものを除き、大きな損傷は生じていませんでした。
.jpg)
主要地方道輪島浦上線光浦トンネル(輪島市光浦付近)の損傷状況 被害は軽微
地すべり防止指定地や急傾斜地崩壊危険区域においては人家や道路に近接している箇所を優先的に崩土除去や水抜きボーリングを行ってきました。
.jpg)
地震による地すべり災害(輪島市門前町地原)
正直、本当にきついものがあった……9月豪雨
河川は34河川で流木や土砂堆積、護岸崩壊が生じた……来年の出水期までに仮復旧が終えられるよう、全力を挙げて工事を進める
――しかし、その矢先に豪雨が生じました
寺田 正直、本当にきついものがありました。新たな路肩やのり面・斜面の崩壊が生じ、県内では不通区間は25路線48箇所になりました。新たな不通区間のほとんどが奥能登で生じたものです。しかし、地震の復旧で多くの業者が現地にいたこともあって素早く崩土除去などを行うことができ、一週間ほどで孤立集落を解消することができました。
道路構造物では、県管理橋で流された橋はありませんでしたが、橋台の背面盛土の流失により、一時的に不通になった橋梁は5箇所で生じました。五十洲橋、中田橋(いずれも輪島市)、折戸大橋、塩津橋、粟津橋(いずれも珠洲市)です。いずれもすぐに背面盛土を復旧させ、すぐに通れるようにしました。
トンネルは北河内トンネルで、トンネル自体に大きな損傷はなかったものの、前後の坑口部の法面が崩壊しました。トンネル出口北側では法面の崩壊により、通行止めとなっております。また、南側についても法面が崩壊しましたが、土砂の除去が完了しております。トンネル内部はひび割れなどが生じている状況です。
河川は34河川で流木や土砂堆積、護岸崩壊が生じました。あまりにも大きな被害で、珠洲大谷川や南志見川水系は県で対応できる範囲を超えており、国による権限代行で復旧・復興を仰いでいます。他の県管理河川で損傷が生じた水系、河原田川、南志見川、八ケ川、若山川も含め、なんとか来年の出水期までに仮復旧が終えられるよう、全力を挙げて工事を進めています。
.jpg)
.jpg)
豪雨により損傷した河川①(左は河原田川(輪島市横地町、右は南志見川(輪島市里町)))
.jpg)
.jpg)
輪島市町野町鈴屋付近の鈴屋川(町野川水系)の護岸損傷状況(当社特約カメラマン撮影)






町野町中心部に近い五里分交差点付近は大きな被害を蒙っていた(国による権限代行で復旧・復興を目指す)(井手迫瑞樹撮影)
.jpg)
.jpg)
八ケ川浦上川の被災状況①(当社特約カメラマン撮影)




八ケ川浦上川の被災状況②(井手迫瑞樹撮影)
――豪雨災害は直接的な損壊もさることながら、業務面でも心理面でも市民の方々や、出先機関で復旧業務を担う職員の方々に対して打撃を与えたことは想像に難くありません
寺田 豪雨災害は、地震後に進めていた仮復旧のかなりの部分に文字通り「衝撃」を与えました。災害査定もかなりの部分でやり直しとなりました。とりわけ2市2町の住民の方々にとっては地震後半年以上が経って、ようやく前を向きかけていた時に、このように大きな災害に遭遇し、本当に心に重い打撃をこうむられたと思います。
――地震や水害の把握には、国土交通省においては多くの箇所でドローンによる把握やその後の仮復旧への点群データの活用が行われていますが、被害の大きかった奥能登総合事務所においては、どのように活用されましたか
寺田 崩壊が大きかった個所では、現地測量が困難であったことから、ドローンを活用した点群データから、平面図や横断図の作成を進め、復旧工法の検討や、災害査定資料の作成などに活用しました。
――その後の進捗状況を具体的に教えて下さい。まず橋梁については
寺田 橋梁については、踏掛け版の無い箇所もあり、段差が多くの箇所で生じました。応急復旧としては擦り付けで対応していましたが、今後は本復旧として、必要に応じて踏掛け版を設置する工事も進めていきます。まだ設計段階であり、具体的な箇所数はお答えできませんが、市町へのアクセス道路等緊急性の高い道路を優先的に進めていく予定です。
流域治水という考え方をもとに対策を進める
盛土 ジオテキスタイルや補強盛土などを用いた強い構造物で復旧
――同様に河川や盛土、のり面および急傾斜面などについては
寺田 流域治水という考え方をもとに対策を進めていくことになります。今回の豪雨ではハードだけでは対応が難しく、尊い人命を守るためにはソフトも活用していかなくてはならないという事が浮き彫りになったと考えています。さらに例えば河原田川水系は地盤の隆起により河床の形状も変わっており、河川をどのように対策すれば必要な流量を確保できるのかを探るのも難しい状況です。そのため、国・県・市町が協議を行い、住居をどこに戻すのか? 川の拡幅や護岸をどのように設置し、どこに道路や橋梁をつくるのか、また、遊水池の設置や、農地の保水能力をどのように加味していくのか? などを考えていく必要があります。こうしたことから、具体的に河川を原形復旧で対応していくのか、もしくは何らかの改良を加味した形で復旧していくのかという事については、これからの課題となります。
.jpg)
豪雨による土石流災害(輪島市山本町付近)
盛土復旧については、崩壊した盛土構造が強度的に劣っていた箇所で生じたことから、地盤などを考慮し、ジオテキスタイルや補強盛土などを用いた強い構造物で復旧していきます。現時点では着手個所はありません。また設計を進めている途中であり、補修構造として確定した個所がありません。
法面・斜面については、モルタル吹付による応急復旧など進めると共に、今後は本復旧として、法枠や鉄筋挿入、アンカー工法をベースとした補修補強を進めていきます。現時点では着手個所はありません。また設計を進めている途中であり、補修構造として確定した個所がありません。
輪島市上山町地内.jpg)
モルタル吹付による応急復旧例(輪島市上山町地内)








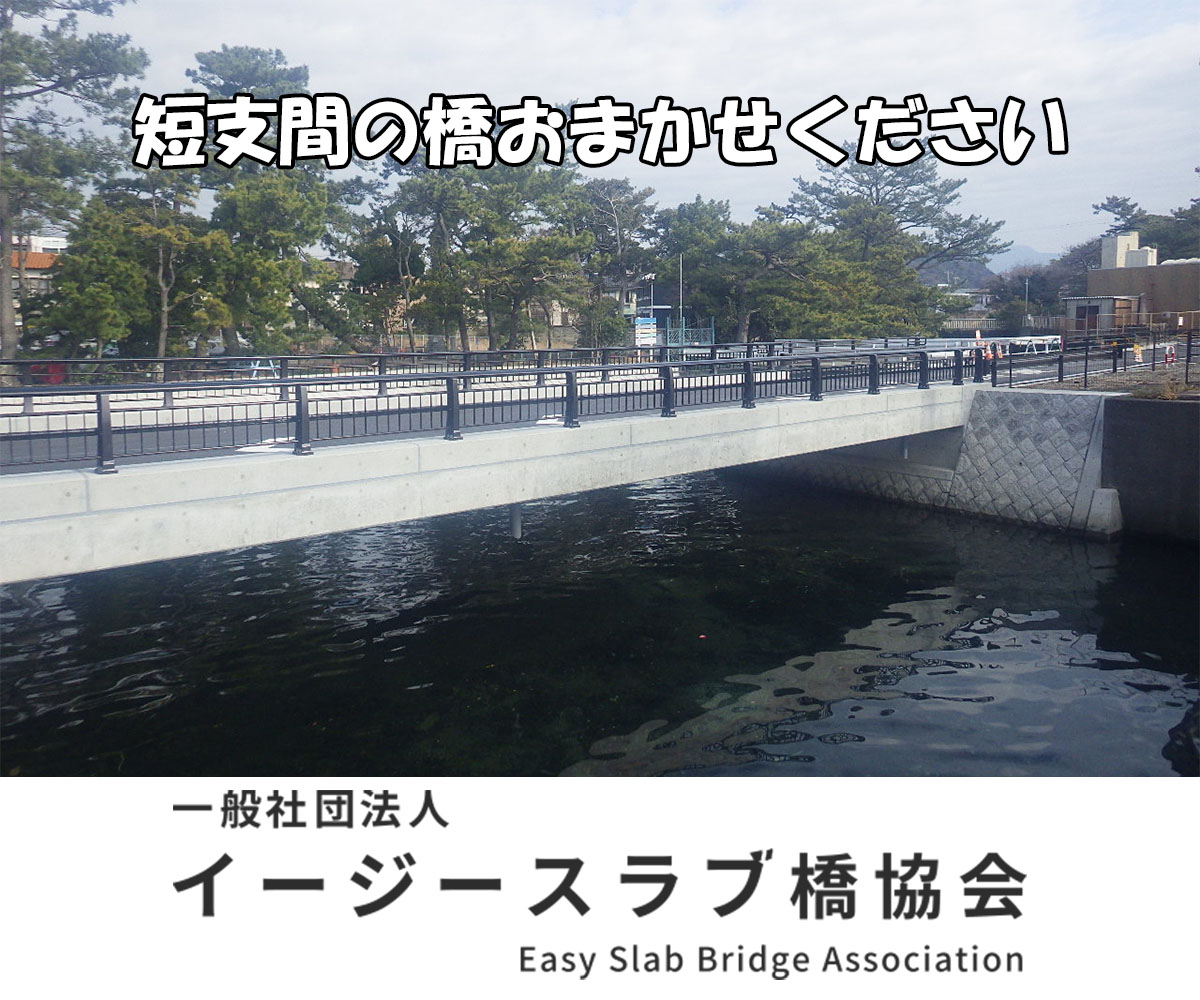





 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら