能登復興特集① 奥能登の復旧・復興状況
災害時への備え……通信の確保、仮設トイレやシャワーの確保も必須
空港ビルは停電しており、他のライフラインも使えない状態 当初は通信も不能
トイレは、2週間以上たってからようやく4台の簡易トイレが提供
――さて、話はいったん変わります。地震発災時の職員および幹部の状況と、その後の対応および人員の増員について教えて下さい
寺田 発災時私は住居のある穴水町にいました。事務所は通常時最大80人ほどの体制で動いていますが、奥能登は非常に被害が大きく、所員も奥能登土木総合事務所の管外から勤務している人も多く、各地で道路が寸断されており、発災後もすぐには集合できない状態でした。
私も奥能登土木総合事務所本庁舎がある輪島市中心地区には、当日は到達できず、まず防災道の駅としての機能も備えたのと里山空港内に入りました。同空港内には事務所の分室もあり、ここから連絡が取れると考えたからです。
しかし、空港ビルは停電しており、他のライフラインも使えない状態でした。そして極寒の中で、避難してきた住民の方々により、ほどなく駐車場は満車になりました。その避難してきた方々に「どの道路が通れるか、どこで被災が生じているか?」を聞き取るなど情報収集することに努めました。
翌日、輪島の本庁舎に到着しましたが、ここにも津波や地震からの避難所として庁舎内には多くの方が避難していました。本庁舎も水道などのライフラインは使えず、僅かに電気だけが通っていた状態でした。本庁舎も通信機能が使用不可能で、本庁との連絡は取りにくい状態にありました。それだけでなく、所員の安否確認もままならず、ようやく全員の安否確認が完了し、体制が整ってきたのは5日目ごろだったかと、記憶しています。
――通信ができないというのは非常に厳しい状況ですね
寺田 厳しいです。通信がつながらないと本庁や他の土木事務所などと連絡が取れないだけでなく、業者との連絡もとれず、初動もままなりません。そんな状況下でもとにかく被害状況の調査を行い、管内全域の把握に努め、県庁への報告のとりまとめに尽力していました。
しかし、ここで課題であったのは道路の渋滞です。
――道路が寸断された状態で渋滞ですか
寺田 そうです。仮に通れるようになった箇所でも一車線しか確保できなかったり、路面の凹凸で減速を余儀なくされたりするなど道路交通の容量は著しく減少する一方で、圏外に避難しようとする車、あるいは圏外から救援に向かおうとする作業用の車などが交錯し、渋滞を引き起こしてしまいました。これが被害の把握を一時的に困難にしました。
――必需物資の供給は
寺田 水はほどなく自衛隊の救援活動により供給されるようになりました。さらに食料は、所員が週末金沢などに帰る際に、大量に物資を買い出し、月曜日に戻ってくる際に搬入することで当座を凌ぎました。ありがたいことに他の事務所からの援助もありました。
トイレは、2週間以上たってからようやく4台の簡易トイレが提供されました。それまでは、中能登土木総合事務所でも聞かれたと思いますが、レジ袋のようなものを広げてその中に用を足すことを行っていました。ようやく断水が解消され、水洗トイレを使えるようになったのは、実に3月下旬でした。
――携帯電話等通信が回復したのは
寺田 携帯電話については、発災直後からつながりにくい状況となっていましたが、民間事業者で仮設のアンテナの設置などを進めた結果、1週間程度すぎたあたりから、連絡がつくようになったようでした。
災害時への備え……通信の確保、仮設トイレやシャワーの確保も必須
自家発電設備の充実、食料や水の備蓄も重要
――今後、こうした災害に対応するためにどのようなことが必要でしょうか
寺田 通信の確保は必須です。さらには、自家発電設備の充実、食料や水の備蓄も重要です。さらには、仮設トイレの相当数の確保や仮設シャワー設備の確保は、職員の士気のためにもバイタルなものであると考えます。水は飲み水だけでなく、手洗いなどに用いる生活用水の循環設備というのも必要ではないかと思っています。
道路の強靱化と景観の調和を図り復旧・復興
文化や自然を大事にしてきた能登の良さを前面に打ち出す
――復旧・復興のために必要な新技術の導入について教えて下さい
寺田 プレキャスト部材の活用や、ICT土工など、省力化・省人化および施工の効率化が期待できる新技術の導入は積極的に行っていきたいと考えています。(※実際の活用事例があれば示してください)現時点での活用はありません。
――今後のまちづくり(コンパクトシティ的な側面も含む)や景観、各種産業や観光業、農漁業などに配慮して強靭かつ風光明媚な道路や河川をどのように両立させていくかについてお答えください。
寺田 能登の里山里海は2011年に世界農業遺産に認定されており、長い歴史の中で育まれてきた産業文化を守り、次世代へ継承していくことが求められています。また、能登半島の海沿いを周回するルートは、眺望に優れるとともに、点在する観光地を繋ぐ重要な道路であります。
これらの風光明媚な観光地への回遊性向上のため、昨年策定した石川県創造的復興プランにおいて、沿岸部の道路を能登半島絶景街道と位置づけ、復旧に合わせて道路の強靱化と景観の調和を図りながら、ビュースポットや自転車走行環境などの整備を進めていくことを、その中で盛り込んでいます。
2月3日には国、県、市町、有識者から成る能登半島絶景街道の創造的復興に向けた検討会が開催され、利用促進政策や情報発信について議論しています。
その他、河川、海岸などの施設については、地盤の隆起や津波による影響、海浜眺望への配慮、利水関係者との調整に加えて市町や地域が策定する復興まちづくりの計画や、流域治水の観点を踏まえた復旧整備が必要だと思われます。
今後、被災者の生活再建、なりわいの再興、新たな地域の再生に向けて、住民や事業者の意見を参考にしながら、これまでの長い歴史の中で、文化や自然を大事にしてきた能登の良さを前面に打ち出した未来への復興を目指していきたいと思います。
――ありがとうございました








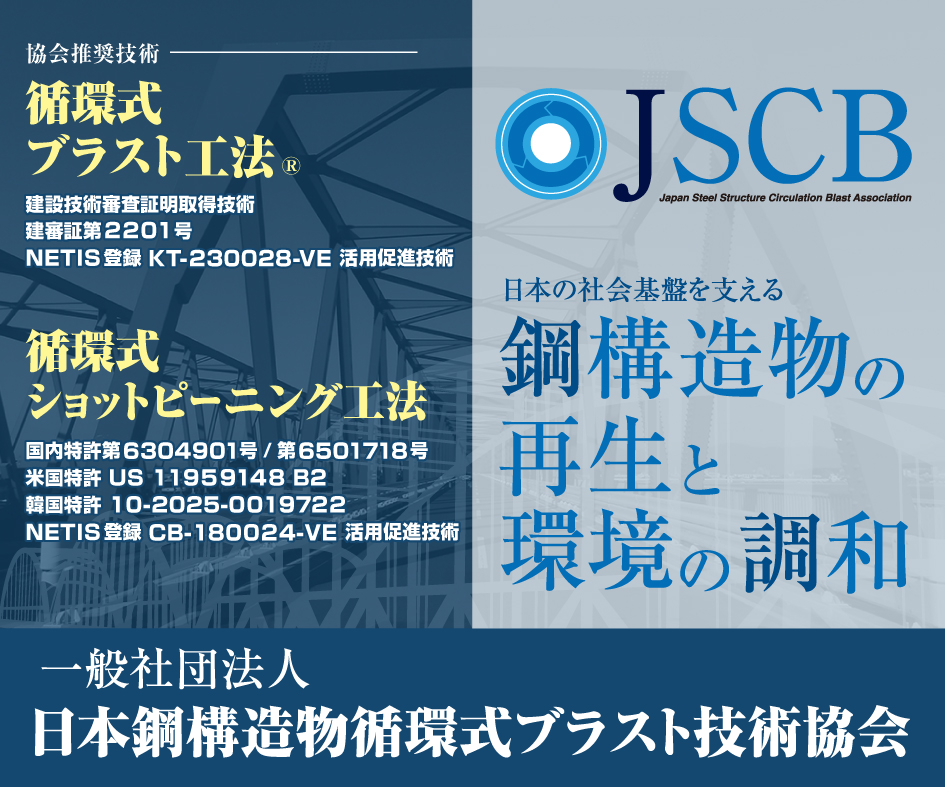




 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら