識者連載
まちづくり効果を高める橋梁デザイン
2.Matthew Wells:『30 Bridges』,2002
続いて紹介するのは、イギリスの構造エンジニアであるマシュー・ウェルズさんによる本です。タイトルのとおり、30橋の興味深い欧米の事例が紹介されています。2002年の出版で、1990年代を中心に著名な橋が収録されています。
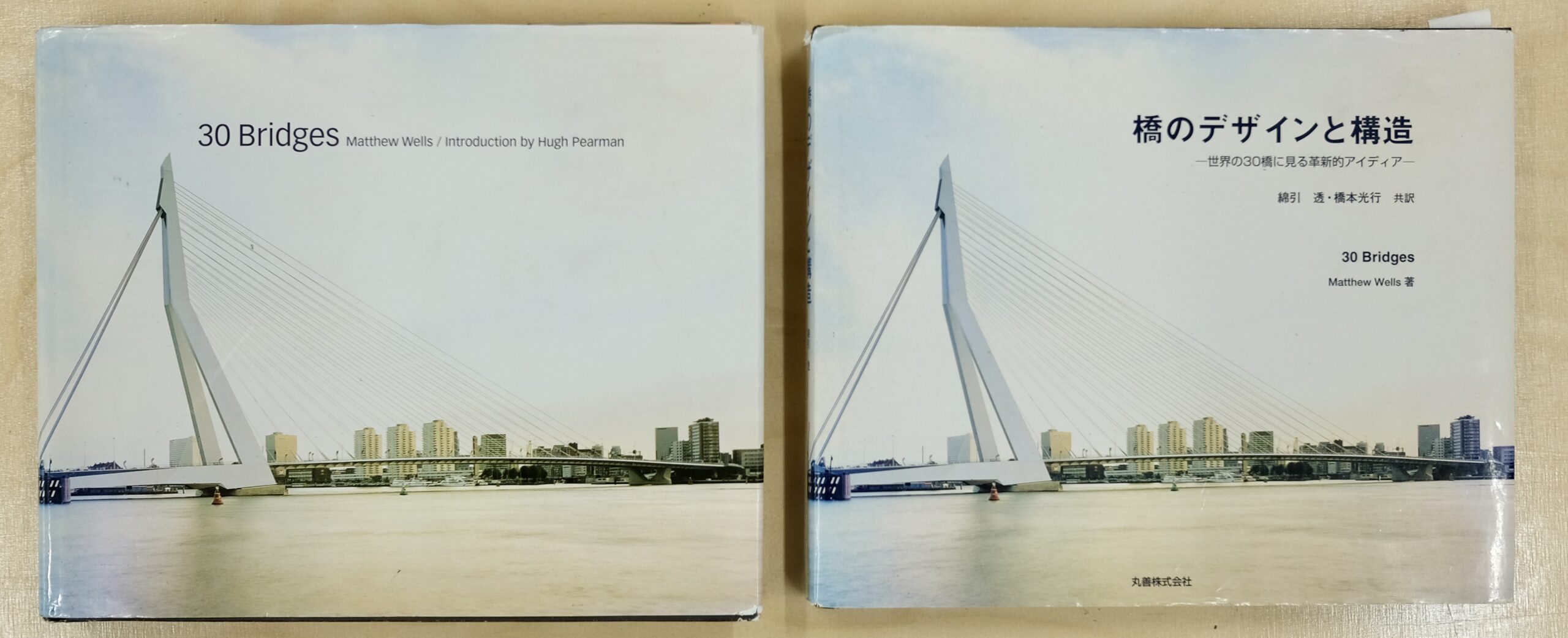
写真3:『30 Bridges』の原著と日本語版の表紙
この本の特徴は、なんといってもウェルズさんによる構造の図解です。なぜそのような形になっているのか、そこにどのような工夫があるのかが、図と文章で解説されていてとてもわかりやすいです。また、ディテールの写真や図面も多く掲載されているので、ディテールを考える際にも役にたちます。ちなみに、日本の橋は、MIHO Museum歩道橋と牛深ハイヤ大橋が取り上げられています。
本書は、原著出版から1年後の2003年に、綿引透さんと橋本光行さんによる翻訳版『橋のデザインと構造ー世界の30橋に見る革新的アイディア』が丸善から出版されていますので、ありがたいことに日本語で読むことができます。
3.Ursula Baus、Mike Schlaich:『Fussgängerbrücken. Konstruktion, Gestalt, Geschichte』,2007
3冊目は、約90橋の歩道橋を紹介した本です。著者は、建築評論家のウルズラ・バウズさんと、ベルリン工科大学の教授で、シュライヒ・ベルガーマン・パートナーの取締役でもあるマイク・シュライヒさんです。
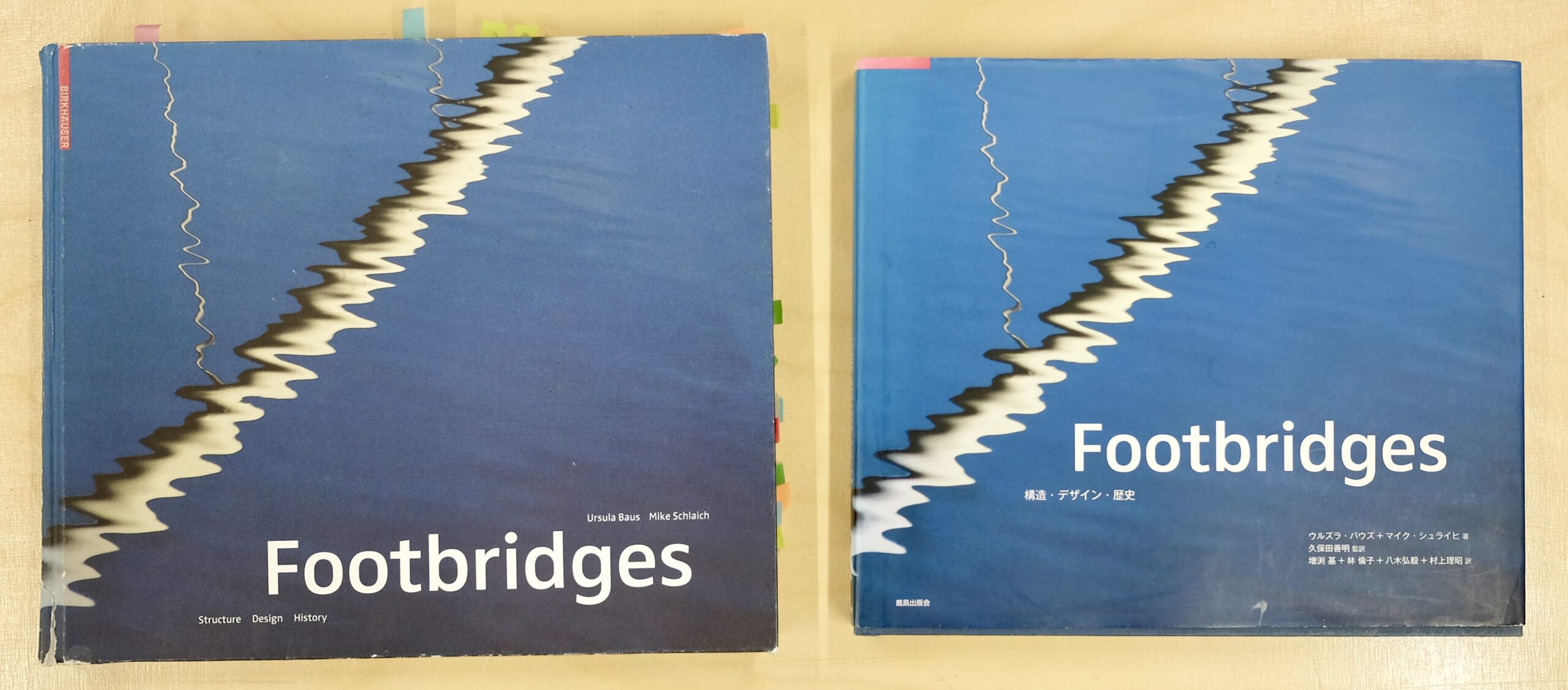
写真4:『Fussgängerbrücken』の英語版と日本語版の表紙
日本で歩道橋といえば道路を跨ぐ横断歩道橋のイメージが強いですが、ヨーロッパには川にかかる歩道橋が多く、ずっと羨ましく思っていました。ですから、本書の序文で、歩道橋にはこれまであまり光が当てられてこなかったと書かれているのを見て驚いた記憶があります。
最初に読んだ当時は把握できていませんでしたが、ヨーロッパでは1980年代に自動車優先の都市計画に対する見直しが意識され、1990年代から都市再生に向けた取り組みがさまざまに展開します。本書で取り上げられている橋も1990年から2000年代前半に集中していることを考えると、都市再生の流れのなかで歩道橋のニーズが高まり、ようやく光が当たるようになったということなのだと思います。
日本は現在、多くの市町村が「ウォーカブル」を掲げて、まちづくりに取り組んでいます。そう考えると、今後、横断歩道橋ではない、歩道橋が増えていく可能性もありますし、そう変えていけたらといいなと思います。
さて歩道橋は、線形の自由度が高い上に、車道橋に比べて荷重が小さいことから、構造的にも空間的にも面白い事例が多く、車道橋への展開も含め、歩道橋から得ることは多いです。橋に対する常識を壊し、視野を広げたい方には特にお勧めできる本です。
また、事例紹介の合間に、技術解説が挟まれているのも魅力的で、吊床版や曲線橋、屋根付き橋、可動橋などが取り上げられています。本書も日本語で読むことができます。タイトルは『Footbridges 構造・デザイン・歴史』で、富山大学の久保田善明先生監訳のもと、故・増渕基さん、関西大学の林倫子さん、日建設計の八木弘樹さん、日本設計の村上理昭さんが翻訳を担当され、鹿島出版会から出版されています。
4.土木学会編:『ペデ:まちをつむぐ歩道橋デザイン』,鹿島出版会,2006
4冊目は、土木学会構造工学委員会の立体横断施設のユニバーサルデザインに関する研究小委員会(委員長:増渕文男先生)による本で、こちらも歩道橋に焦点を絞った本となっています。
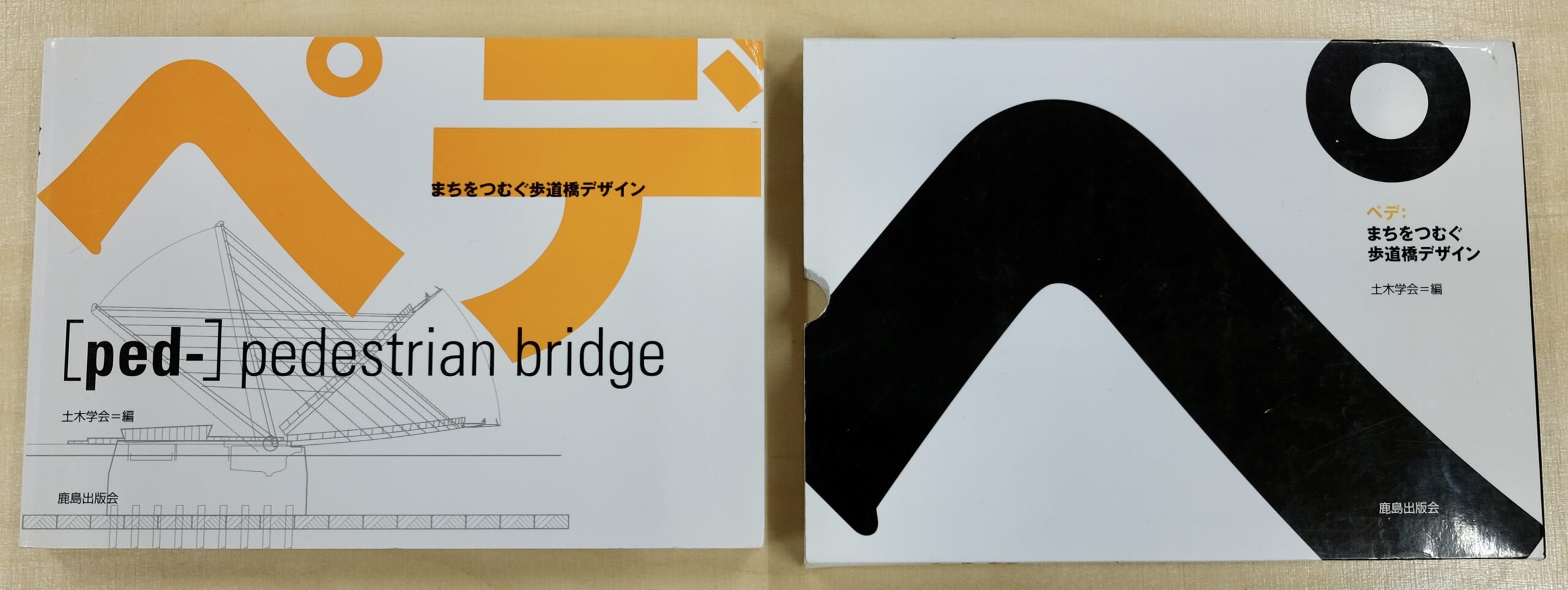
写真5:『ペデ:まちをつむぐ歩道橋デザイン』の表紙と函
横断歩道橋や駅のペデストリアンデッキについても詳しく触れられていますが、本書がカバーしている内容はもっと広く、都市デザインの観点から橋を捉え、都市の回遊性を高め、人々の滞留を促す橋のありかたについてまとめられています。
本書を読み進めると、日本にも横断歩道橋ではない歩道橋をもっと増やそうという思いがひしひしと伝わってきます。出版時期的にウォーカブルという言葉こそ使われていませんが、メンバーの皆さんはそれを意識されていたと思います。20年ほど前に出された本ですが、今こそ読み直したい、読みたい一冊です。
主構造の素材や構造の基本、舗装材料や照明などにも触れられているので、学生の皆さんにもおすすめです。本の装丁もかっこいいですよね。















 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら