まちづくり効果を高める橋梁デザイン
5.久保田善明:『橋のディテール図鑑-写真でみるヨーロッパの構造デザイン』,鹿島出版会,2010
5冊目は、富山大学の久保田善明先生による本で、東京大学名誉教授の伊藤學先生が監修された『橋のディテール図鑑-写真でみるヨーロッパの構造デザイン』です。
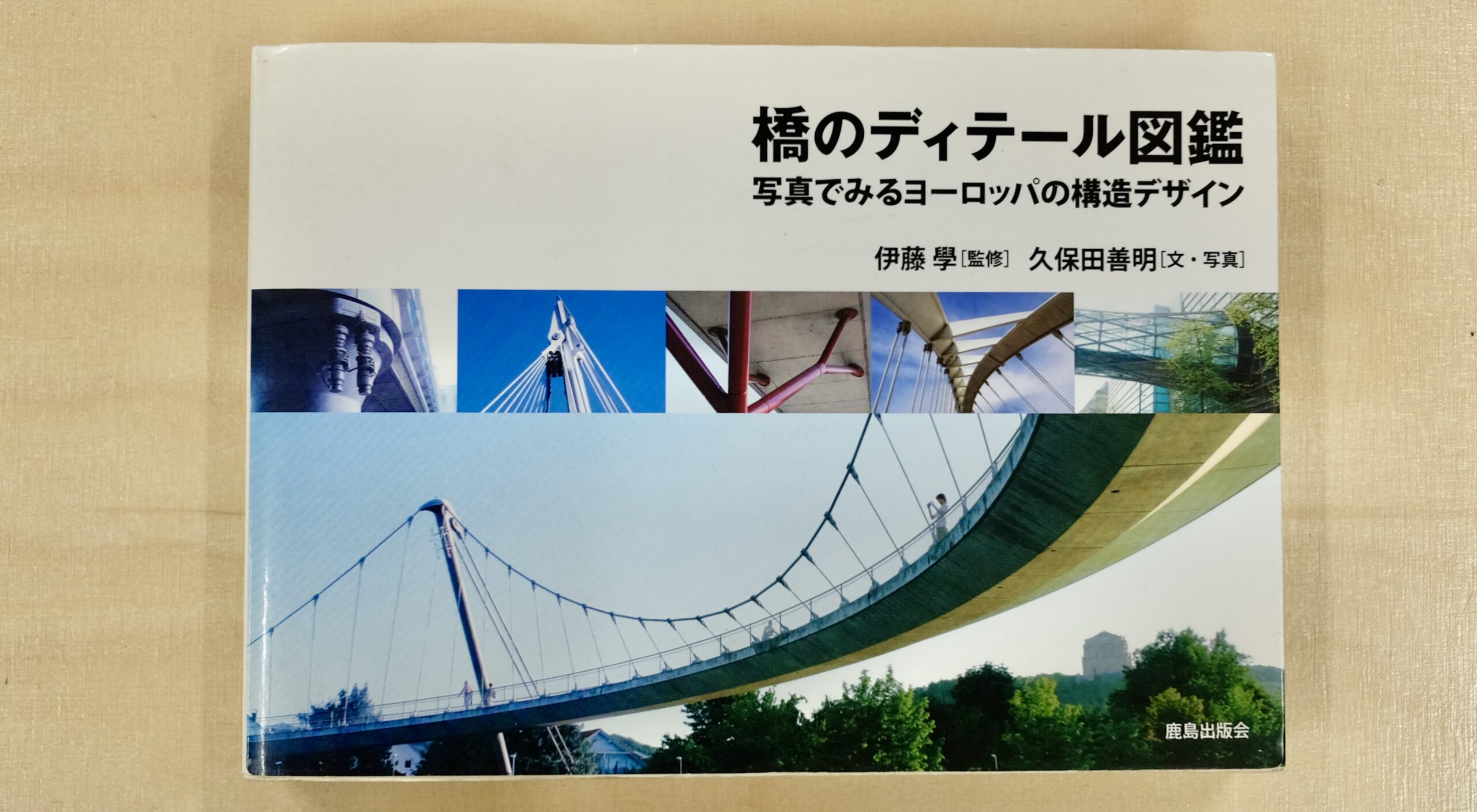
写真6:『橋のディテール図鑑-写真でみるヨーロッパの構造デザイン』の表紙
設計を進めていくと、この接合部はどのように処理するのがよいのかとか、どうやればきれいに収めることができるのか、パーツはどの程度のサイズになるのかなど、ディテールの部分で悩むことも多いと思います。橋の出来上がりの印象に大きく影響するので、ディテールはとても重要なのですが、参照できる書籍が少ないのが現状です。
そこで手元に置いておきたいのが本書です。A5横サイズの小さな本ですが、ヨーロッパの80橋について、様々な角度から撮影されたディテールの写真が掲載されているので、写真を見ながらディテールのイメージを膨らますことができます。本を見ることで、現地視察で注目したいポイントも学ぶことができます。
写真を眺めると、やはり図面が気になってきます。そんなときは橋の名前で検索することをお勧めします。図面や製作・施工写真がヒットする可能性もあります。ちなみに本書には橋の位置座標も掲載されているので、訪れる際にも、Googleマップのストリートビューを使う場合にも便利です。
6.Thorsten Helbig, Michael Kleiser, Ludolf Krontal:『Bridges Potentialities and Perspectives』,2021
6冊目は、ドイツのDetail Architecture社が発刊する書籍シリーズEdition Detailの橋の特集本です。2021年の発刊で、今回紹介する本の中では最も新しい本です。ドイツ語版と英語版があります。
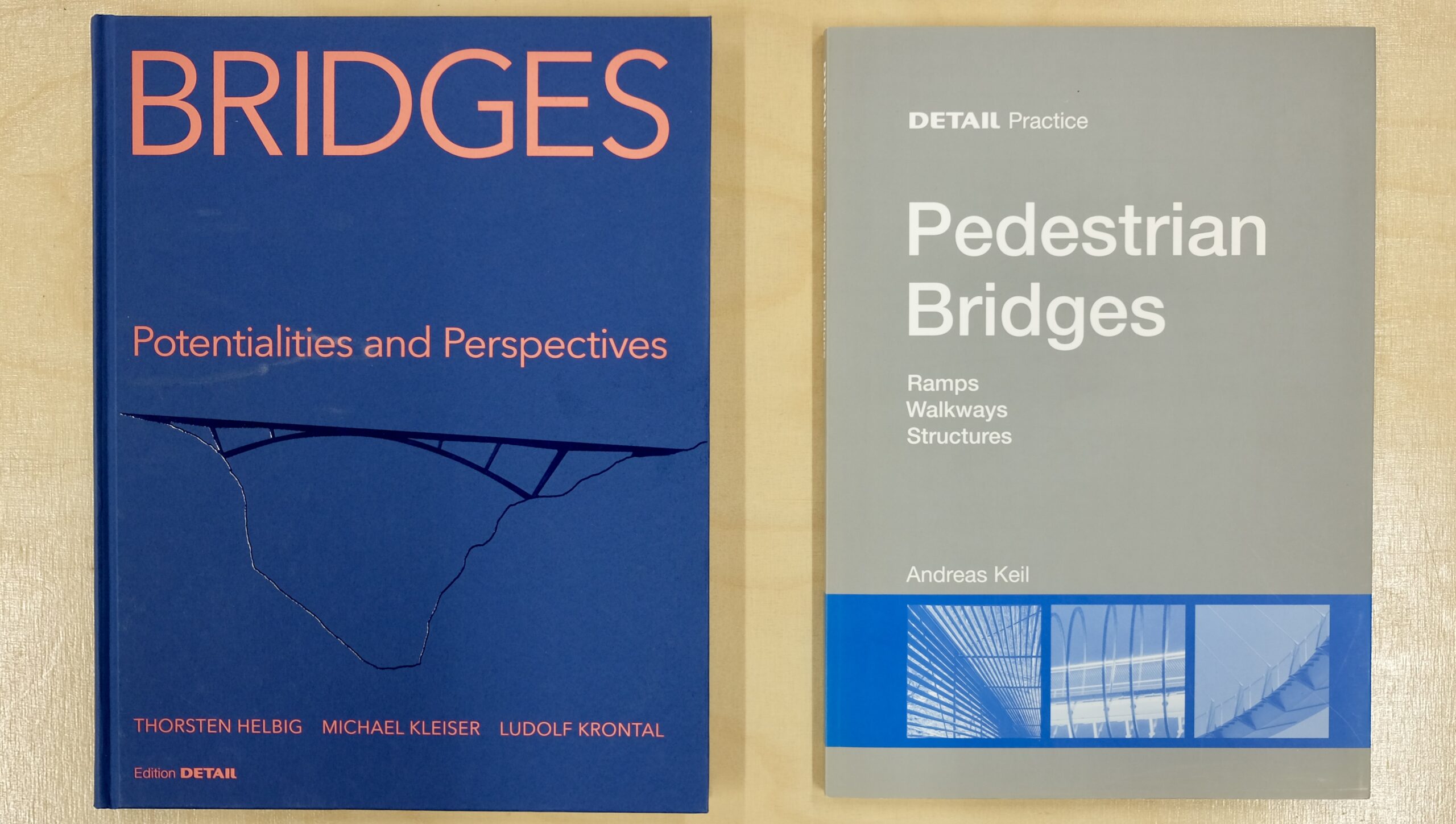
写真7:『Bridges』と『Pedestrian Bridges』の表紙
橋の事例紹介を主眼に置いた本というよりは、橋のこれからのあり方から、荷重や機能、経済性や維持管理といった橋の要件、木材や3Dプリンターを含む素材、構造システムのカタログ、10の具体的な事例を取り上げ、図面とともに解説という構成になっていて、橋の設計にかかわる事項を広く取り扱っているのが特徴です。
これらの項目とともに取り上げられている事例も興味深く、海外の橋梁設計の動向も知りつつ、魅力的な橋に触れたいという方にはとくにおすすめです。
ちなみに、序文の「橋-その可能性と展望」は、多くの刺激的な橋梁デザインを提案し実現しているイギリスの橋梁デザイン事務所Knight Architectsを主宰するMartin Knightさんが書かれています。
印象的な部分を紹介しますと、「橋の設計者として、私たちは思考の枠組みを「成果としての橋そのもの」から「橋によってどのような効果が生まれるのか」、あるいは「橋そのもの」から「橋を使う人」へと転換する必要がある。つまり、「このプロジェクトはなぜ必要なのか?」、「誰に影響を与えるのか?」という問いに真剣に向かい合い、徹底的に考える必要がある」
今の時代は、インフラが一定の充実を得て、橋の必要性が誰にとっても自明ではなくなった時代ですよね。交通という機能を超えて、橋は人々にどのような価値を提供できるのかが求められている。そうしたパラダイムシフトを意識することの重要さにに共感します。
せっかくですので、簡単に目次を記しておきます。
・橋-その可能性と展望
・橋の建設ー過去・現在・未来
・要求事項(荷重・機能・経済性・長寿命)
・素材(木材・石材・鉄・コンクリート・ファイバーなど)
・デザイン(構造システムのカタログ)
・橋梁の詳細ー歩道橋・道路橋・鉄道橋合わせて10の事例
ちなみに、Detail Architecture社のサイトを見ると、セール価格で販売しています(2025年4月29日現在)。
https://www.detail.de/de_en/bridges?srsltid=AfmBOoqvz3a23E0hrplews8Q0I4r4A1mMHBVJy63sZjKEz6nMM89JLuW
7.Andreas Keil:『Pedestrian Bridges : Ramps, Walkways, Structure』,2013
最後は、同じくドイツのDetail Architecture社が発刊するDetail Practiceというシリーズで、こちらは歩道橋を取り上げた本です。出版年は2013年で、先ほどの本より8年ほど早く出版されています。著者は、シュライヒ・ベルガーマン・パートナーに1985年から在籍し、これまでにDeutscher Brückenbaupreis(ドイツ橋梁建設賞)をはじめ、数々の賞を受賞している橋梁エンジニアのアンドレアス・ケイルさんです。
こちらも、橋の事例紹介を主眼に置いた本というよりは、歩道橋の設計をひととおり解説するものです。その項目は、基本的な要求事項(幅員や建築限界、昇降施設)、静的・動的解析、素材、構造形式ごとの設計と施工、舗装や手すり、排水などの橋面、ライフサイクルコストを含む経済性、可動橋や展望台といった特殊な橋、そして最後に9つの事例を取り上げ、桁断面などの図面とともに解説が行われています。
歩道橋全般について広く取り扱っていて、かつ掲載している事例がいずれも魅力的ですので、社内や仲間で輪読するのも楽しい本ではないかと思います。
今回もご覧いただきありがとうございました。次回の内容はできれば維持管理とデザインの両立をテーマにしたいと思っています。6月末頃を予定しておりますので、どうぞよろしくお願いします。









.jpg)




 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら