進化2025は最終段階 増大する事業量にいかに対応するか
点検補修の進化、大規模更新や耐震補強の進捗状況
J-システムやAuto CIMAで効率的な点検にチャレンジ
取得した点検データもデジタル化
――点検補修の進化について。人手不足の中でこの分野の技術開発は頓に必要になってくると思いますが
前川 道路法が改正されて省令点検が平成26年度から始まって1巡目が平成30年までかかりました。その時は、点検は子会社のエンジニアリング会社が担当していましたが、とにかく人手が足りないということで、いかに人手を確保して省令点検を行うか、ということが一番の課題でした。そのため近接目視と打音で膨大な構造物を点検するための体制づくりを行いながら進めました。2巡目は令和元年度から始まり、この3月までで終わりましたが、点検支援技術をかなり導入しています。当社はJ-システムやAuto CIMA(オートシーマ)など実用化の域にあった技術を保有していました。それにさらにドローンを加えて、いかに効率的に点検するかということをチャレンジした2巡目だったと思っています。


Jシステムの実施例


Auto CIMAによる点検実施例
一番効率化に寄与したと思ったのは、現場におけるタブレットを用いた記録です。現場で記録してしまえば、従来のように野帳に書いて、さらに事務所に帰ってパソコンで記録を制作するような二度手間はなくなりました。当然、取得した点検データもデジタル化できていますし、また、当社の道路はGISの地理空間情報でデジタル化して閲覧することができますので、そのデータと紐づけることで、構造物の場所や点検部位がスムーズに出せるようになっています。
令和6年度から3巡目が始まりますが、1巡目と2巡目を比較することで、劣化が進んでしまった箇所については分析を進めてその要因を突き止め、適切に対処します。土木技術者としては当たり前のことですが、「水が鋼材や鉄筋コンクリートに悪影響を与える」といったことについて、点検データを分析することで定量的に説明が可能となります。補修時期の判断や優先順位、予防保全対策等に活用していきたいと思います。
また、逆に劣化が進行していない箇所もたくさんあります。そうした箇所は点検をしなくても良いとまでは言わないまでも、点検を省力化できないかと考えています。例えば画像だけ撮っておいて、後日、AIやBIツールで解析してみること、などです。そういう意味でも全ての箇所を打音点検まで行う必要は、必ずしもないのではないかと考えています。
大規模更新 契約済みは6割 次は西名阪
契約済み トンネルは3割、グラウンドアンカーは7割が工事中及び完了
――大規模更新・大規模修繕について教えてください。また技術的成果についても教えてください
前川 大規模更新については床版の取替など橋梁関係が主です。橋梁関係でいうと当初計画で対象としたものについてですが、完成しているのが約2割、契約済みは(完成も含めて)約6割、つまり2割が完了していて4割が工事中となっています。現在は関西(中国道・阪和道)、中国(中国道・広島道)、九州(九州道・沖縄道)で全面展開中です。その他の大規模更新・大規模修繕においては、法面やトンネルのインバート設置工などがありますが、トンネルは1割が完了しており、工事中まで含めると2割、グラウンドアンカーなど法面の補強は、5割が完了しており工事中まで入れると7割に達しています。
個別で言いますと中国道の吹田JCT~神戸JCTですが、重交通路線であり、多いところでは10万台近く走っています。また、隣接して交通量の多い国道171号や大阪府道中央環状線が並走しており、それに交差する道路もたくさんあって、交通規制協議や地元説明が大変でした。メインは7回にも及んだ全面通行止めで、その中で既設構造物の撤去、新しい構造物の架替えを順番に行っていきました。例えば架替えの時間を稼ぐためにNEXCOではこれまであまり用いてこなかった鋼床版を採用している橋梁もあります。しかし、他の箇所で同じようなことができるかというと、そうではなく、制約条件や関係機関との協議などによって決まっていくと思います。当然受注された業者の皆さんから色々な知恵も出してもらって、相談しながら作り上げていくものだと思っています。
阪和道の松島高架橋は、人家が非常に接近した箇所にあります。しかも側道もありません。そうした厳しい条件下での工事ということで、資機材の運搬路を高架下に設けるなどの工夫を行っています。同橋は、既設のRC中空床版桁を取っ払って、プレテンPCT桁に替えています。これも所与の条件から施工を担当する会社の技術提案などもあり、採用されたものです。また、昨年秋より隣接の来栖高架橋の床版取替にも着手致しました。新たに泉南IC~和歌山JCTの夜間通行止めによる床版取替にR5年度より着手しています。
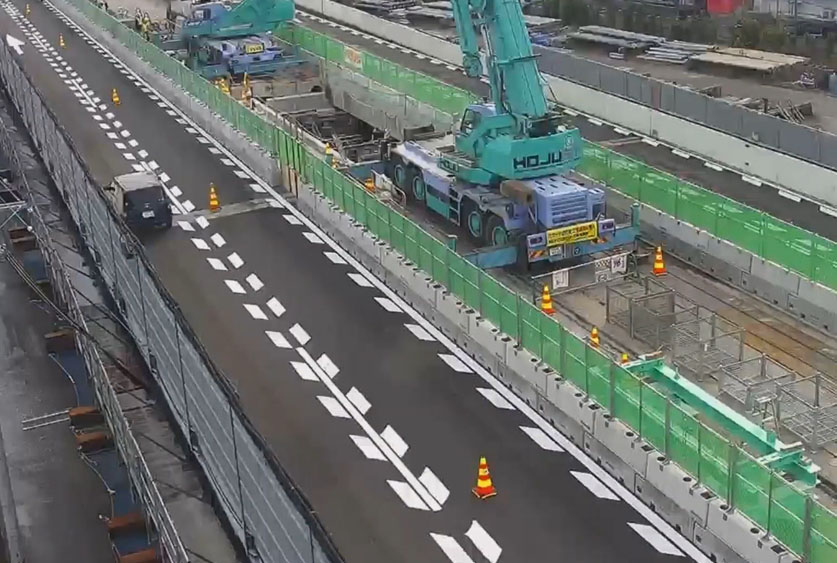

松島高架橋は人家が非常に接近した箇所にあり、既設桁の切断方法も工夫している

SCBR工法で桁架設を行っている




九州道・宝満川橋は3分割施工を行っている

床版の撤去・架設は専用の機械を用いた
――こうした新たに得た経験は、今後さらに重交通な西名阪や近畿道の大規模更新で用いられるものでしょうか
前川 次は西名阪だと思っています。西名阪も建設当時は千日道路といわれる突貫工事で建設されました(当時の建設大臣である河野一郎氏が当時の伊賀大和越えルートの過酷さを痛感して、早く便利なルートを確保した)。名神と近畿道はその後です。名神はRC中空床版桁を多用しており、そこは点検の状況を見て、補修での対応なども選択肢として、最適な対応をしていきたいと考えています。
耐震補強 工事中は588橋、未着手は1,628橋
NEXCO西日本コンサルタンツという自前の設計子会社
――今年の1月に耐震補強の進捗を図るべくNEXCO3社と本四高速が委員会及び共同記者会見を行いました。上下線のどちらか片側を先行して耐震補強を行い、耐震補強を行っていない路線をできるだけ減らしていこうという施策ですが、一方で耐震補強の進まない理由の一つとして入札不調が示されていました。また、険しい箇所では管理用道路もない箇所もあります。NEXCO西日本としては耐震補強事業をどのように進めていこうと考えられていますか
前川 会計検査院からご指摘をいただいたのはその通りです。もともとの耐震補強は倒壊したり、落橋したりするのを防ぐためのもの(耐震性能3)で、その対応はすべて完了しています。現在行っているのは、平成28年に発生した熊本地震での橋梁の損傷を反映し、可及的速やかに復旧できる耐震補強対策(耐震性能2)です。同地震では九州縦貫道の木山川橋や並柳橋において桁が支承から脱落して大きな段差ができました。そうした段差ができてしまうと、緊急車両ぐらいは通すことができますが、一般車両が通ることは難しくなります。
地震発生時に早期に通行機能を復旧させるために、さらなる耐震補強を平成29年から進めています。NEXCO西日本全体の橋梁は6,466橋ありますが、4,250橋が耐震性能2を確保できています。対象橋梁は2,216橋です。そのうち工事中は588橋で、未着手は1,628橋となっています。未着手橋梁については、会計検査院からの指摘も踏まえて、優先順位を考えながら、路線の片側だけでも耐震性能2を確保するようなことをしていきたいと思っています。発生確率が26%以上の地域にかかる橋梁を優先的に対策しています。
対策の遅れや入札不調という話ですが、事業化後にすぐに工事に着手できるという訳ではなく、当然ですが、まずは設計をしなくてはいけない。とりわけ動的解析をやらなくてはいけないわけですが、動的解析を含めて耐震補強が必要かどうかということを判断ができるようなコンサルタントの数、設計技術者の数が足りないことは当初からわかっていました。当社は耐震補強が必要な橋梁の数が多いので、継続契約を行ってきました。一度契約したら、その設計会社に数件続けて行ってもらうというものです。
そういう取組みや、コンサルタントの協力もあって、設計はすごく進みました。設計ができたところから、次の段階である実施工の発注を行っています。これも継続契約方式を取り入れることで、順調に対策は進んでいると思っています。
もちろん、現場に入るために新たに工事用道路を造らなくてはいけないとか、準備工事に時間がかかるということはもちろんあります。それは避けられない部分であり、そうした課題もクリアしながら工事を進めています。
さらに当社にはNEXCO西日本コンサルタンツ(以下、Nコン)という自前の設計子会社があり、そこには橋梁のプロともいうべき人財がいます。








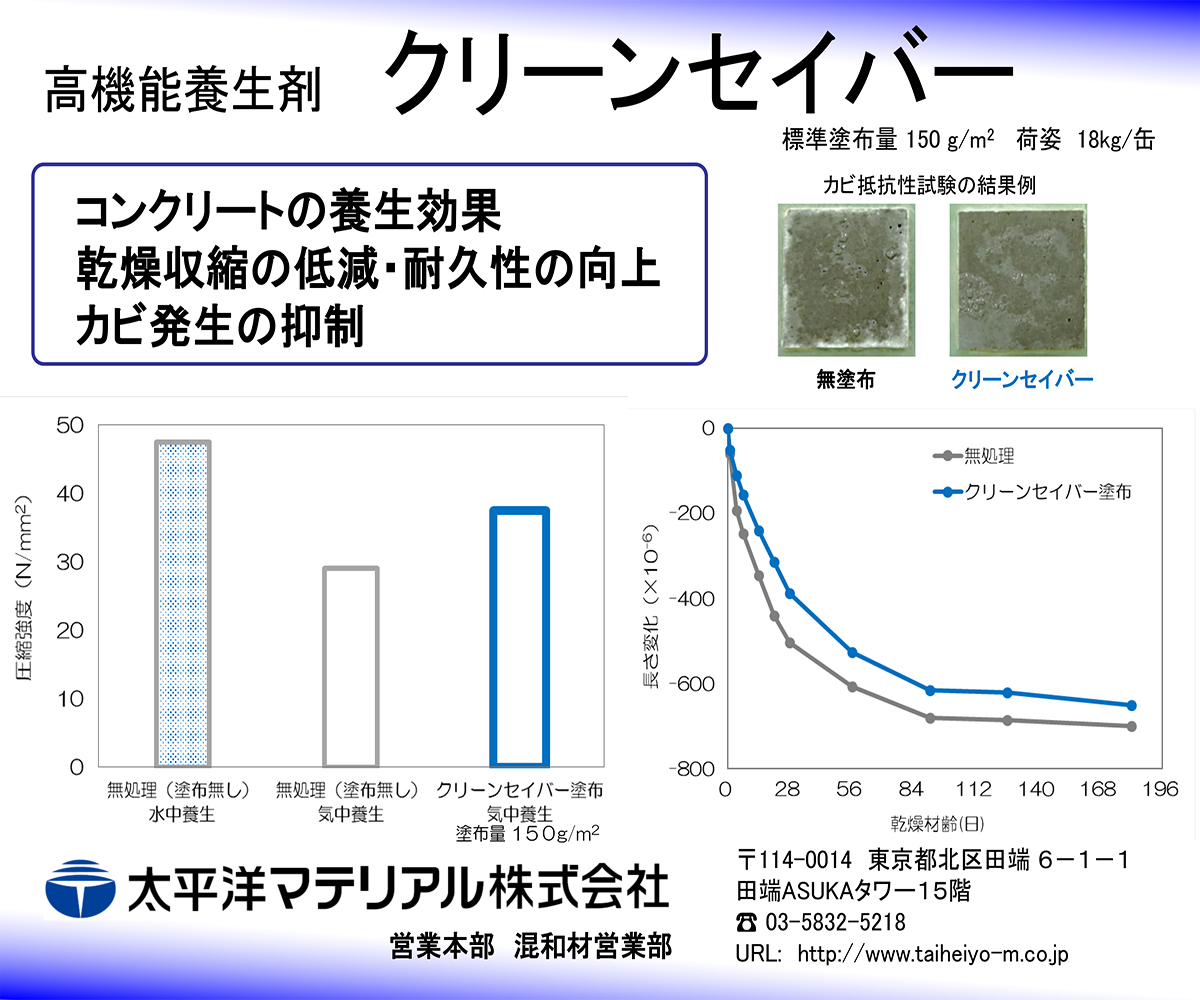





 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら